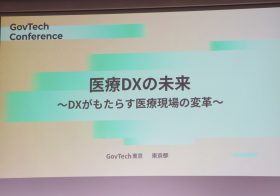日比谷高、東大合格者63人の衝撃…公立高が復権、国公立大学医学部・合格者数ランキング

梅雨に入り、受験生の志望校選びが本格化する時期になった。何事によらず、目標が明確でなければ、楽とはいえない学習を持続することは困難だ。当事者はもとより、保護者にとって、その選定は悩ましいところだろう。
特に中学や高校の志望校選びは、多感な年頃を過ごす学び舎であるとともに、次の進路を考慮しなければならず、大学選びよりも難しい面はある。情報量の面でも、近年詳細な開示を求められている大学ほど豊富とはいえない。受験関連雑誌や週刊誌の特集などを参考にするにしても、その内容は中正とはいいがたい。付き合いの濃淡や、広告の縛りもあるのか、総じて私立校に甘い評価をする傾向が見られるからだ。雑誌類は毎春、通読をしているが、以前よりもバイアスが大きくなっている印象を受ける。
「何がなんでも私立というトレンドの転換点になるのかもしれない」(学習塾関係者)
その根拠になるのは、高校の進学力を示す象徴的な指標、東大合格者の出身校ランキングだ。今年もトップは例のごとく開成高、続いて灘高、筑波大付属駒場高、麻布高など、お馴染みの顔触れになったが、9位に公立校のエース、日比谷高が入った。
「2018年にも10傑入りをしており、それ自体は驚くべきことではないが、注目すべきなのは63人という合格者数」(同)
世に溢れる自称進学校は置くとして、自他共に認めるトップクラスの進学校になるには、長い時間と段階を要するものだ。東大合格者数も最初は1桁、次に2桁にのせ、この水準を安定させて、ようやく地域を代表する進学校として認知される。さらに全国区で名を馳せるには、毎年20人前後の合格者を出す必要はある。
日比谷高の合格者数に意味があるのは、過去10年間で東大合格者が60人を一度でも超えたことのある高校は、開成高、灘高、筑波大付属駒場高、麻布高、桜蔭高、渋谷教育学園幕張高、聖光学院高、栄光学園高、駒場東邦高、西大和学園高(国立の筑波大付属以外は私立)の10校しかないところだろう。
「頂点を形成する一員のお墨付きを得たことになり、これは公立校を見直す流れをさらに強める」(同)
1980年代から90年代にかけて私立進学校全盛時代に受験を経験した保護者たちからは「日比谷高が突出しているだけ」との反論が聞こえてきそうだが、各種のデータからも都内公立校の復活は否定できない。最難関である国公立大学の医学部医学科合格者数を見ても、日比谷高以外の公立進学校も、例年コンスタントに合格者を出しており、「都立高校では医学部合格は無理」との認識は、明らかに過去のものになっている。
時勢もまた、公立校には追い風になるのだろう。昨年来の新型コロナウイルスの跳梁によって、特に一部の業種や職種は壊滅的な打撃を受けた。今後想定される所得格差の拡大で、教育費の捻出に苦慮する所帯はさらに増えるだろう。
地方自治体の授業料補助によって、私立校の学費は以前より安くなったものの、それでも公立校と比較すると大きな差がある。文部科学省が平成30年度に実施した「子供の学習費調査」によれば、1年間に要する学習費の総額は公立高校45万7000円に対して、私立高校は97万円と倍以上になる(同じく私立中学は140万6000円、公立中学は48万8000円)。得られる結果が、ほとんど変わらないとすれば、よほどの思い入れがない限り、いずれの選択が賢明かは、容易にわかることだろう。
【2021年都内主要公立校の国公立大学医学部医学科及び防衛医科大学校の合格者数】
日比谷37人、戸山14人、西12人、国立7人、★武蔵・青山各5人、★九段4人、★小石川、★三鷹、立川各3人、八王子東、★白鷗各2人、★大泉、★桜修館、★両国、★富士、★南多摩各1人
(主要私立校)
★開成62人、★渋谷教育学園幕張41人、★麻布27人、★武蔵15人
※★は中高一貫校、数値は各校ホームページより引用
(文=島野清志/評論家)