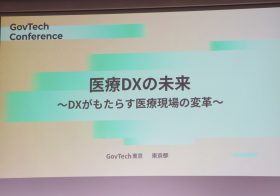中国を排除するIPEFの危険さ…米国が狙う太平洋「経済ブロック化」

米国のレモンド商務長官は5月31日、新たな経済圏構想「インド太平洋経済枠組み(IPEF)」が掲げる(1)デジタル経済を含む貿易、(2)半導体供給などのサプライチェーンの強化、(3)質の高いインフラやグリーン投資、(4)公正な経済を促進するための税制・汚職対策の4本のテーマについて、どの国がどの分野の議論に参加するかは「今夏に決まる」との見通しを示した。「東南アジア諸国が中国の反発を恐れてIPEFへの参加を見送る」との懸念から発足メンバーに入れなかった台湾については「米国にとって極めて重要なパートナーだ」と強調、貿易、投資、技術協力などの分野で二国間協議を進める考えを示した。
IPEFは就任後初めて訪日したバイデン米大統領が5月23日、その始動を表明した。発足メンバーは日本、米国、韓国、インド、豪州、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの13カ国だが、その後フィジーが加わり現時点では14カ国だ。参加する国々の国内総生産(GDP)の合計は世界の4割を占める。トランプ政権時代に環太平洋経済連携協定(TPP)から離脱して以来、インド太平洋地域での経済戦略を持たなかった米国がリーダーシップを取り戻すことが狙いだ。
だが、TPPのような関税引き下げを含む貿易協定は米議会の承認を得られないことから、今回のIPEFには関税分野の交渉が含まれていない。このため「参加国にとっては米国市場の開放という魅力に欠ける」との批判が出ている。それどころか、IPEFが掲げる4つのテーマの具体的な運用を誤ると、生産性の向上どころか、監視や規制の強化でコスト上昇につながる危険性があるとの指摘もある。
IPEFは経済効果の面でTPPと比べて見劣りするのはたしかだ。さらに、これまでの広域経済圏構想とはまったく異なる性質を有していることも見逃してはならない。TPPは高度なレベルで統合された経済連携協定だが、中国のTPPへの参加申請が可能なように、安全保障面での高い要求が課されているわけではない。
一方、IPEFは経済のレベルにとどまらない自由主義と民主主義の価値観を共有する国々の経済安全保障の枠組みであり、中国が加わることを当初から想定していない。IPEFの目的が「中国への対抗を念頭に強靱で公平な経済の構築を目指す」ことであれば、特定国の排除を禁止する「関税及び貿易に関する一般協定(GATT)」第1条に定められた一般的最恵国待遇の原則に反するのではないかとの疑問が呈されている(5月30日付ニューズウィーク)。西側諸国はウクライナに侵攻したロシアへの最恵国待遇を取り消したが、IPEFは戦争が起きる前から中国を交戦国扱いするようなものだといえなくもない。IPEF参加国と中国との関係が今後悪化する可能性がある。
この懸念を明確に指摘したのはIPEF参加国の一つであるマレーシアのマハテイール元首相だ。東京で開かれた第27回国際交流会議「アジアの未来」で講演するために来日したマハテイール氏はNHKのインタビューで「IPEFには中国に反対し米国に友好的な国をつくるという政治的な目的がある。経済発展には安定が重要であり対立は必要ない」と否定的な見方を示した。
世界最適調達システムの時代の終焉?
冷戦終結以降、世界経済のグローバル化は大きく進展した。情報通信技術を活用したコンテナ物流システムの発達で企業のサプライチェーンは国境の壁を越えて拡大し、コスト面で最も適した国で生産された部品が国際的な物流ネットワークを通じて取引されて最終製品に組み立てられるという「世界最適調達システム」が定着した。だが、ロシアのウクライナ侵攻という予想外のリスクの顕在化で「コストを軸にした世界最適調達システムの時代は終わりを迎える」との疑念が高まっている。
国際情勢の悪化を受けて、グローバル化を後押ししてきた経済学よりも世界経済を異なるブロックに分裂しかねない地政学が幅を効かすようになっている。世界は今後、日本、米国、欧州連合(EU)など民主主義に基づき政府の市場への介入を抑制する「自由市場資本主義ブロック」とロシアや中国など専制的で政府による強い市場統制を自認する「国家資本主義ブロック」とに分断され、両ブロックが互いに優位を競う時代になってしまうとの予測まで登場している(5月19日付日本経済新聞)。
中国のアジア支配に歯止めをかけたい米国には「IPEFをインド太平洋版EUのような価値観を制度で担保する政治同盟に発展していきたいとの思惑がある」との見方もある(5月23日付ニューズウィーク)。IPEFが自由市場資本主義ブロックに発展していく可能性は排除できない。これに刺激されてロシアや中国などが国家資本主義ブロックの形成を急ぐような事態になれば、世界経済の分断は決定的になってしまうだろう。
国際通貨基金(IMF)は5月下旬、「世界経済は現在、第2次世界大戦後で最悪の状況にある。何十年にもわたって築いてきた経済統合が解消されれば、世界はさらに貧しくなる上に危険性も高まる」と警鐘を鳴らした。ブルームバーグ・エコノミクスも同時期に「グローバル化の反転加速が長期的に何をもたらすか」についての分析結果を公表した。示されたのは「世界貿易の規模は中国が世界貿易機関(WTO)に加盟する以前の水準に戻り、希少となった商品価格の上昇でインフレの高進が進む」という豊かさが大きく失われる世界だ。
グローバル化にも弊害はあるが、ブロック化のほうがはるかに実害が大きい。国際社会はなんとしてでも世界経済の分断化を防がなければならない。
(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)