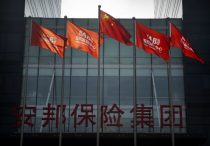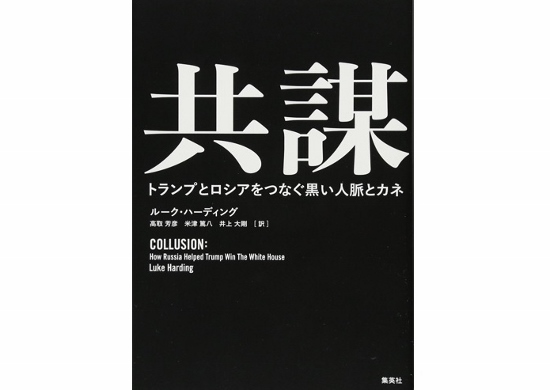 『共謀 トランプとロシアをつなぐ黒い人脈とカネ』(集英社/ルーク・ハーディング著、高取芳彦、米津篤八、井上大剛訳)
『共謀 トランプとロシアをつなぐ黒い人脈とカネ』(集英社/ルーク・ハーディング著、高取芳彦、米津篤八、井上大剛訳)中国製品への制裁関税適用、シリア攻撃など、通商・軍事面の大きな決断が目立つアメリカのドナルド・トランプ大統領。しかし、彼の「大統領としての資質」を問う声は、いまだアメリカ国内に根強く残っている。
その源は、いうまでもなく「ロシア疑惑」である。これは、ロシアがサイバー攻撃などによって2016年のアメリカ大統領選挙に干渉し、「トランプ陣営と結託していたのではないか」とされる問題だ。追及が進む一方でいまだ決定的な証拠は見つかっていないが、さまざまな関係者の証言から、少しずつ全貌が明らかになってきている感もある。
その最たるものが、『共謀 トランプとロシアをつなぐ黒い人脈とカネ』(集英社/ルーク・ハーディング著、高取芳彦、米津篤八、井上大剛訳)である。イギリスのジャーナリストであるルーク・ハーディング氏は、ロシア側も含む膨大な数の関係者への取材によって、「ロシア疑惑」というあまりにも大きな「絵」の空白を埋めていく。
この連載では、ロシア疑惑にまつわる基本的な疑問を、本書をお供に紐解いていく。第3回となる今回は、疑惑発覚後のロシアで行われている情報機関職員の粛清がテーマである。
ロシアで相次ぐ、関係者の拘束や不審死
「ロシア疑惑」を告発したのは、元イギリス秘密情報部(MI6)の工作員であるクリストファー・スティール氏である。彼が残した諜報メモには、ロシアとトランプ氏の共謀の事実や、トランプ氏がロシアに決定的な弱みを握られていることなどが記されていた。
諜報関係に限らず、あらゆる告発において関係者が気になるのは、その情報がどこからもたらされたのかである。告発を受けた側はそれを明らかにして情報の正確性を計ろうとし、ときには「犯人探し」をする。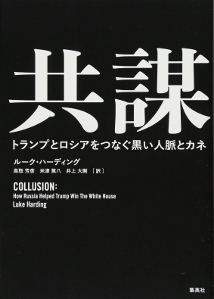 『共謀 トランプとロシアをつなぐ黒い人脈とカネ』(集英社/ルーク・ハーディング著、高取芳彦、米津篤八、井上大剛訳)
『共謀 トランプとロシアをつなぐ黒い人脈とカネ』(集英社/ルーク・ハーディング著、高取芳彦、米津篤八、井上大剛訳)
本書では、複数のFSB職員が事実と認めている、こんな話を取り上げている。16年12月、スティール氏のメモが各国の情報機関やメディアの間でひそかに話題になっていた頃、FSB職員が集う講堂で、サイバー活動を担う「情報セキュリティーセンター」の副センター長であったセルゲイ・ミハイロフ大佐が、近づいてきた男に突然頭から袋をかぶせられ、クラッキングとサイバーセキュリティの専門家である部下2人と共に連行された。この衝撃的な拘束劇は、FSB筋によってテレビ局や新聞社に伝えられ拡散した。
ミハイロフ大佐には以前から機密情報を他国に渡した容疑がかけられていたことを踏まえると、一連の出来事の意味合いを読み取るのは難しくない。「裏切り者は同じ運命をたどる」というメッセージを伝えるための見せしめである。
『共謀 トランプとロシアをつなぐ黒い人脈とカネ』 機密文書のリークが発端となった「ロシア疑惑」は、トランプ政権の閣僚、スタッフが次々と辞任、起訴に追い込まれ、大統領本人の聴取をめぐってFBIとトランプ側の攻防が繰り広げられている。そもそも、トランプとロシアが結びつくきっかけは何だったのか、誰が関わっているのか。細かい取材の積み重ねで、複雑なルートが少しずつ明らかになっていく。