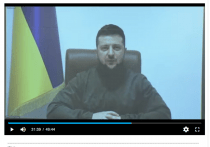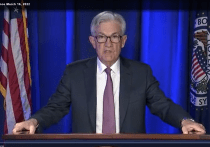ロシア封じ込め、世界に浸透せず、3分の1の国がロシアに賛同…欧米の差別的対応に不信

4月11日にモスクワでプーチン大統領と会談したオーストリアのネハンマー首相が17日放映の米NBCテレビ番組で「プーチン大統領は侵攻を正当化する『独自の戦争論理』に浸っており、ウクライナとの戦争に勝っていると思っている」と述べたことが話題となっている。プーチン大統領が西側諸国の認識と正反対の見解を示したからだ。ウクライナに侵攻したロシアに対する厳しい制裁を科した西柄諸国では「ロシアは国際社会から完全に孤立し、敗北しつつある」との見方が常識化している。だが、西側諸国にとっても「不都合な真実」が明らかになりつつある。
ロシアがウクライナに侵攻してから2カ月が経とうとしているが、新興国のほとんどがロシアの侵攻を支持するか、中立の立場をとっており、西側諸国による「ロシア封じ込め」が国際社会で一向に浸透しないという由々しき事態となっているのだ。
英誌エコノミスト(4月16日号)は人口分布に着目した分析を行っている。それによれば、ロシアを非難し制裁にも加わっている国の人口は世界の3分の1にすぎない。ほとんどが西側諸国の国民だ。次の3分の1は中立の立場をとる国に住んでいる。インドなどの大国やサウジアラビア、アラブ首長国(UAE)といった中東地域における米国の同盟国などだ。残りの3分の1はロシアが主張する侵攻の口実に賛同する国の住民だ。このグループで最も人口が多いのは中国だ。
新興国が西側諸国に同調しない理由として食糧や兵器をロシアに頼っていることが挙げられることが多い。親ロシアのプロパガンダが広がり、「プーチン支持者」が増加しているとの指摘もあるが、プロパガンダを真実と受け止める土壌があることも事実だ。
白人優先主義への非難
問題の本質はもっと深刻である可能性が高いようだ。前述のエコノミストは「西側諸国を退廃的で利己的な偽善の塊だとみなしている国が少なくない」と指摘しているが、どういうことだろうか。
新興国の間で西側諸国への対応への不満がこれまでになく高まっており、特に中東地域でこの傾向が顕著だ。中東地域の人々は、西側諸国でウクライナ国民に対する同情が急速に高まっていることについて不信感を募らせてきた。欧米諸国は避難するウクライナ人に対して門戸を喜んで開放しているが、かつてシリアからの難民が流入した際、どれだけ冷たい態度をとったことか。西側諸国は普遍的な権利を口にするが、ウクライナへの対応が中東地域に向けられた態度とあまりに違う。「白人優先主義だ」との非難が高まるばかりだ。
アフリカでも人道危機における国際社会の対応が「人種差別的」だと不満が強まっており、エチオピア出身の世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長もその一人だ。13日の記者会見でテドロス氏は「黒人と白人に影響を及ぼしている緊急事態をめぐり世界の関心に偏りがある」と訴えた。同氏は「ウクライナに対する支援はとても大事だ」としながらも「人道危機に陥っているエチオピアやイエメン、アフガニスタン、シリアなどはウクライナと同等の注目を受けていない」と指摘している。
ロシアへの制裁についても「ダブルスタンダードだ」との批判が出ている。「外国への侵攻」という意味では米軍のイラク侵攻も同じだが、「国際社会は米国に制裁を科したのか」との怒りがこみ上がってきている。西側諸国は都合のいい時だけ連帯を求め、そうでなければ背を向ける。新興国が「信用できない」と考えるのは当然なのかもしれない。
過去の植民地支配への怒り
新興国が反発する背景に過去の植民地支配への根深い怒りがあることも気になるところだ。4月14日付ロイターは「西側諸国に対する積年の恨みが発展途上国全体に広がっている」と報じている。「対中包囲網」形成の目的で西側諸国が接近しているインドでも同様の状況だ。 「『国際社会はロシア糾弾で団結した』とする理解は欧米人の希望的勘違いにすぎない」とインドでは受け止められている。
独立してから75年しか経っていないインド人の脳裏に英国支配下の人権蹂躙の記憶が鮮明に残っており、植民地時代の積もり積もった不満から「欧米人に人権や民主主義について説教される筋合いはない」との反発が広まっている。西側諸国が米国主導の国際秩序の再構築を目指しているのに対し、インドは「米国の一極支配構造は崩れ、世界は多極化に向かっている」と理解しており、国際秩序に関する認識についても大きなずれが生じている。
かつて「世界の警察官」だった米軍のアフガニスタンからのぶざまな撤退ぶりも暗い影を落としている。新興国で「米国はいざというときに頼りにならない」との理解が広まり、「米国の同盟国であることは利益よりも不利益のほうが大きいのではないか」との懐疑が芽生えつつある。
一方、ロシアはシリア内戦への介入以降、中東地域などで存在感を高めつつある。「力こそ正義」というプーチン大統領の世界観は西側諸国では過去の遺物だとみなされている。残念なことだが、この世界観が今後国際社会で一定の支持を得ることになってしまうのではないだろうか。
(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)