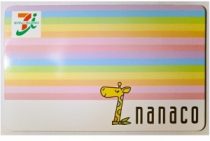「Tサイト」より
「Tサイト」より3月27日付当サイト記事『ツタヤ図書館、税金を使ってTカード会員勧誘…貸出カード作成者に勧誘DM』で報じたように、3月21日にリニューアルオープンした宮城県多賀城市立図書館では、同館の指定管理者であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)の非常識な公私混同ぶりが浮かび上がり、激しい批判にさらされている。
佐賀県武雄市、神奈川県海老名市に続いて「ツタヤ図書館」として生まれ変わった同館においても、Tカード機能付き図書カードが選択肢のひとつとして採用されている。
それについては、これまで個人情報保護の観点から、情報がCCCサイドに漏れるおそれがあるとの批判が繰り返しなされてきたが、実はTカードの基本機能自体がCCCにとって金儲けの種なのである。つまり、公共図書館が公式にTカードを採用することは、結果的にCCCへの利益供与となっているのだ。
まずここで、Tカードの仕組みを解説しておこう。まず、加盟店でTカードを提示して商品を購入、またはサービスを利用した会員には、通常100円ごとに1ポイント(加盟店によっては200円ごとに1ポイント)が付与される。その一方で、Tカードの提示を受けた加盟店は、その客が支払った金額の2%を手数料としてCCCに払う。会員に付与するポイントも加盟店負担のため、合わせて購入額の3%程度を加盟店は負担しているのだ。
さらに、加盟金5万5000円、毎月7500円のシステム使用料の固定費がかかるため、加盟店の負担は決して軽くはない。
Tカード会員は加盟店で買い物するたびにポイントをもらえるが、加盟店は2倍以上の手数料と固定費とポイント相当分をCCCに支払っているため、その分が販売価格に転嫁されているケースもある。つまり、ポイントがつくからといってTカード加盟店で商品を購入することが必ずしもオトクなわけではないのだ。
では、会員によって使われるポイントは誰が負担するのか。貯まったポイントを会員が加盟店で支払いとして使うと、加盟店はその分だけ一時的に入金は減るが、そのポイント相当分は翌月CCCから返金される。
つまり、会員が購入した金額の1%相当がポイント付与されるが、ポイントはCCCにプールされており、そこから使用されたポイント分が加盟店に返金される。ポイントの倍以上の手数料がCCCに納付され、さらに使われないまま失効するポイント分はそのままCCCの利益となる。ポイントビジネスは、かなり収益性が高く、かつ損のない事業といえる。
Tカード採用はCCCへの利益供与か
客が加盟店で支払った代金の数%が手数料になるという意味では、手数料の率こそ低いものの、クレジットカードと同じような収益構造になっていることがわかる。つまり、TカードはCCCにとって、継続して手数料収入をもたらしてくれる「自動集金ツール」となっている。
それにもかかわらず、ツタヤ図書館を誘致した自治体では、図書カードにTカード機能を付加するにあたっては、そうしたTカード本来の手数料収入について基本的な仕組みを詳しく検討した形跡がまったくみられない。
ポイントが付く便利機能を図書の貸し出しカードと一体化させることで、市民の利便性が向上する。なおかつ、既存のTカードを図書カードとして使うことで、新規にカードを発行する費用が大幅に削減されるとツタヤ図書館を誘致した自治体は市民に説明している。
しかし現実には、CCCにしてみれば労せずにTカード会員を獲得でき、会員増加に伴って手数料収入も増加するカラクリなのだ。
このように、公益性以上に私的利益が大きい事業を行政が後押しし、それどころか税金を使って会員獲得キャンペーンを展開しているのだから、常識を逸脱した利益供与と言わざるを得ない。
クレジットカード業界関係者は、こう話す。
「クレカ同士の新規会員獲得合戦が、年々エスカレートしています。楽天カードのように入会特典として5000ポイント付与するのはもはや当たり前で、Yahoo!JAPANカードは8000ポイント付与、なかには期間限定で実質1万5000円相当のポイントがもらえるカードもあります」
Tカードは、あくまでポイントカードであってクレカとは違うと思う向きもあるかもしれないが、Tカード作成にあたってCCCは厳密な本人確認書類の提示を求めているため、結果的に精度の高い個人情報を保持している。それをツタヤ図書館では、施設内店舗の無料券を2枚贈呈するだけで獲得できるのだから、相当にコストパフォーマンスは高いといえる。
しかも、大人以上に価値が高いといわれる子供の個人情報ですら、図書館利用カードとの名目で大量に獲得できるのだから、CCCにとっては非常に大きなメリットだ。
図書館の運営に際して、税金から運営委託費をもらっている一民間企業が、さらに自社の私的なポイントサービス会員の拡大を図ることは、果たして適切な行為といえるのだろうか。ツタヤ図書館は、公正な競争を阻害しているのではないかという疑問が拭えない。
(文=日向咲嗣/ジャーナリスト)