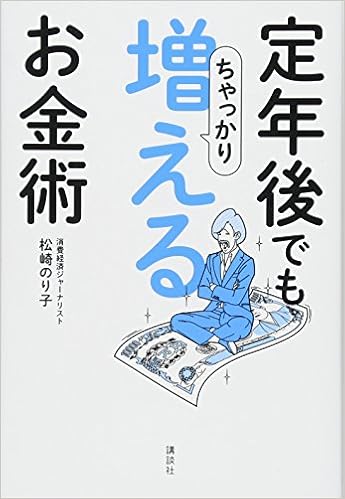10月1日の消費税率引き上げと同時に、鳴り物入りでスタートしたキャッシュレス還元制度。政府の発表によると、1~7日までの1週間に還元されたポイントは、1日平均約8億2000万円相当に上るという。
このままのペースでいくと予算額を使い切るのではという声もあるようだが、それはどうだろう。スタートダッシュの勢いはあるが、毎日そこまで買い物はできない。とはいえ、冬のボーナスや年末年始商戦、外食では忘年会・新年会あたりでひと盛り上がりはくるだろう。
今回のキャッシュレス還元事業の対象外である大手家電量販店や大手デパート・流通各社も、やはり別立てのポイント還元策や決済事業者のキャンペーンに乗って、消費熱を煽っている。来年6月までに、どれほどの消費額が積み上がることだろうか。
とはいえ、今はキャッシュレスを語りたいわけではない。なぜ、我々がこの施策によって素直に買い物をしてしまうのか。その仕組みを知り、本来は必要なかった買い物を防ぐための提案をしたい。
そのキーワードとなるのが、「フレーミング効果」というものだ。簡単に言えば、同じことを示していても、表現の違いによって異なる印象を与えられる効果のことである。
たとえば、こんな具合だ。婚活パーティーの参加者募集で「実績では参加者の約4割がカップル成立!」と聞けば、まずまずと感じる。しかし、「6割の参加者は相手を見つけられなかった」と言われたらどうだろう。表現している事象は同じなのだが、受ける印象はまるで違う。
おなじみの100円ショップも、フレーミング効果をうまく利用していると言える。「すべて100円!」と聞けば、どの品も安いという印象を持つが、実際には割高だったり、ほかの業態なら100円以下で買えたりする物も紛れている。しかし、「100円均一」というフレームでひとくくりにされると、すべてが安いだろうと錯覚してしまうのだ。
「ポイント失効前に駆け込み消費」の罠
このフレーミング効果は、「ポイント」でも効果的に利用されている。日本人はポイント好きと言われ、常になんらかのポイントを貯めている。そして、それが失効するのが、とにかく苦痛なのだ。
覚えのある人も多いだろうが、手元に期間限定ポイントがあるとしよう。「もうすぐ期限が切れるポイントが150ポイントあります」と言われると、それを無視できる強心臓の持ち主はなかなかいない。手元のポイントが失効する前に、あわてて何か買おうと考える。しかし、有効期限まで時間がないので、熟考している余裕はない。150ポイントを消費できればいいので、特に必要がないものでも飛びついてしまうのだ。その気持ちは実によくわかる。
しかし、ここで考えるべきなのは、150ポイントとはどんな価値なのかということだ。賢明な読者はお気づきだろう。これは、現金相当額の表現をポイントに変えただけだ。150ポイントというともったいない気がするが、これが1ポイント1円相当だとすれば、実質150円となる。はした金とまでは言わないが、「150ポイント」と言われるより「150円」と認識したほうが、冷静に損得判断ができるのではないだろうか。
「○%」より実際の数字で計算してみよう
このように、150ポイントは惜しいが150円となるとテンションが下がるとすれば、「フレーミング効果」にはムダ買いを喚起する作用があるということだ。
今回の消費税の税率アップにも、似たような作用がある。私たちは税率10%と聞くと、「それは大変だ、1割も払うお金がアップするのか」と思いがちだが、そうではない。上がるのは9月までの8%に対し、2%分だけだ。「消費税が10%になる」のと「消費税が8%から2%上がる」は同じことを示しているのに、駆け込み購入を誘う文句としては「10%になる」のほうが効果的なのは言うまでもない。
たとえば、3万円の商品を買うとして、10月以降に買えば3万3000円になってしまうじゃないかとあわてるわけだが、9月まででも3万2400円は払うのだ。差額は600円。これも小さい金額ではないが、びっくりするほどの差かと言えばどうか。
今回も9月の最終日に向かって、さまざまな駆け込み購入が起きたという。特にテイッシュやトイレットペーパー、紙おむつなどの日用品が売れ、近所のドラッグストアもレジは長蛇の列だったし、棚が空っぽになった店舗もあったとか。しかし、実際に税率アップ後に買うといくら余計に払うかは、実計算してみればすぐにわかる。350円のテイッシュを2組買ったとして計算すると、増税前後の差額はわずか14円。大混雑しているレジに並ぶ価値があるかは微妙だろう。
最初に挙げたポイント還元策も、2%や5%という還元率につい目が行くが、実際の数字だとどうか。コンビニなどフランチャイズ店は2%還元となっているが、ランチに500円分の食品を購入したとすると10円の還元だ。5%還元対象のショップで5000円の買い物をした場合、還元額は250円。むろん、現金で買うと還元はないので、たとえ10円でも250円でもトクはトクだ。しかし、「何がなんでもキャッシュレスで買わないと損だ!」と勢いづくほどの金額ではない(消費税は含めずに計算)。
ポイントや還元率だけを見ていると、「とにかく買わないと損だ」「このポイントをムダにしたくない」と浮足立ってしまいがちだが、そういうときこそ「では、実際いくら損をするのか」「いくらトクなのか」を計算してみるべきだ。身近な金額で示されると、その魔法は解ける。
ムダ買いを防ぐ簡単なコツ
「10円でも安いほうがいいに決まっている」という声も聞こえてきそうだ。もちろん、その通り。きちんとレシートを見て、「今日は10円トクできた、よかった」と実感できるなら。
しかし、我々の周囲には、リアルの金額がピンと来ないような「オトク感」の演出が満ち溢れている。ポイントや還元率、割引率と、そこで表記されている数字だけ見れば、購買意欲が刺激されるものばかりだ。もし還元ポイント目当てで大きな買い物をしようとしているなら、「自分はこの商品を買っていくらトクするのか。還元策が終了した後と比べて、どのくらい損をするのか」を計算してみるほうがいい。実数字を見てこそ、損得の判断が冷静にでき、買う・買わないの裁定も下せるはずだから。
キャッシュレス決済にはほかにもメリットはあるが、今それを使っている人の多くは還元策が目当てだろう。だとすればなおさら、むやみに買い物をする前に、まずは電卓を叩いてみることをお勧めする。
『定年後でもちゃっかり増えるお金術』 まだ間に合う!! どうすればいいか、具体的に知りたい人へ。貧乏老後にならないために、人生後半からはストレスはためずにお金は貯める。定年前から始めたい定年後だから始められる賢い貯蓄術のヒント。