Facebookも新たに開始…主要SNSの「収益化プログラム」を比較・整理してみた
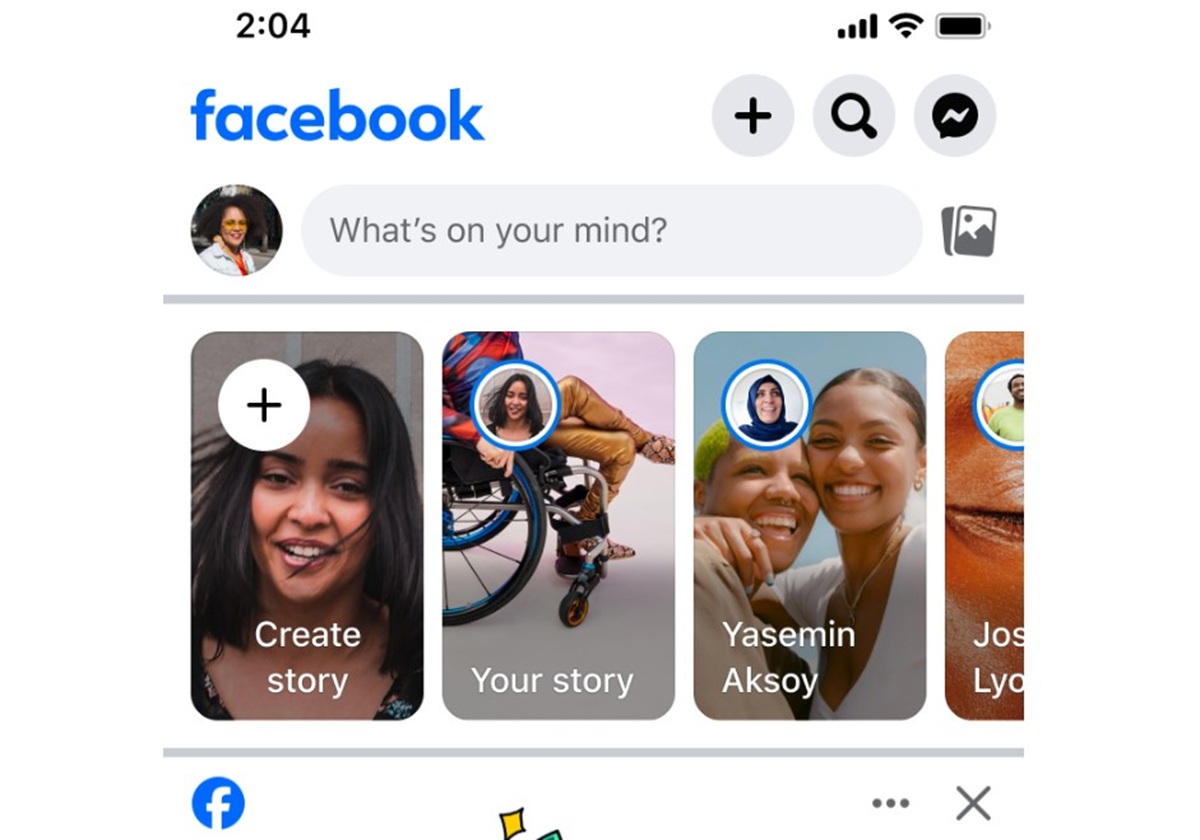
●この記事のポイント
・Facebookは2024年、新たな収益化プログラムをリリース
・主要なSNSでは収益化の仕組みが多様化しており、プラットフォームごとの特徴を理解し、適切に選択・運用することが重要
・短期的な拡散力を求める場合はTikTok、案件収益を狙うならInstagram
Facebookは昨年(2024年)、新たな収益化プログラムをリリースし、海外では10万ドル(約1500万円)以上の収益を見込む企業も出始めているという情報もあり、Facebookはクリエイターに報酬を支払う方針を強めている。Facebookに限らず、YouTube、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokなど他のメジャーなSNSも収益化プログラムに類する仕組みを提供している。それぞれ、どのような特徴があるのか。また、どのような使い分け方をすれば、より大きな収益を上げやすいのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
●目次
各SNSの収益化プログラムの特徴
高額な広告収入を公表する人気YouTuber(ユーチューバー)もいるため、SNSでの収益化と聞いて真っ先に思い浮かぶのがYouTubeだろう。例えばYouTubeパートナープログラムで収益を得るためには、まず同プログラムに申請するための条件である「チャンネル登録者数500人以上」「直近90日間にアップロードした公開動画3本以上」「直近12カ月間の公開動画の総再生時間3000時間以上、または直近90日間のショート動画の視聴回数が300万回以上」などを満たす必要がある。さらに同プログラムに登録した上で広告収益化機能を有効にするためには、「チャンネルの登録者数1000人以上」「直近12カ月の動画総再生時間が4000時間以上、または直近90日間のショート動画の視聴回数が1000万回以上」などの条件を満たす必要がある(いずれも2025年5月末時点)。広告再生回数1回あたりの収入は動画によって差があり、ここ数年、その金額は低下傾向にあるとされる。
各SNSの収益化プログラムの特徴について、運用型 SNS・インフルエンサー広告プラットフォーム「INFLUFECT(インフルフェクト)」を提供するリデル株式会社は次のように説明する。
「現在、主要なSNSでは収益化の仕組みが多様化しており、クリエイターにとってはプラットフォームごとの特徴を理解し、適切に選択・運用することが重要になっています。
YouTubeは、動画再生による広告収益を主軸とした『YouTubeパートナープログラム』が非常に安定しており、長尺コンテンツや教育・解説系のジャンルとの相性が良いです。また、スーパーチャットやメンバーシップなどの追加機能も充実しています。
Instagramでは、直接的な広告収益制度は限定的ですが、企業とのタイアップやブランド案件による収益が主流です。クライアントコミュニケーションと共感性に長けたクリエイティブやコンテンツを作成できる方に向いています。
TikTokは、再生回数に応じた報酬を得られるクリエイター向けのプログラムや、ライブ配信時のギフト機能が用意されています。拡散力が高く、短期間でバズを狙いたいクリエイターに適しています。
Facebookは、Reelsによる広告収益や、Stars(投げ銭)、サブスクリプション機能などがあります。ただし、日本国内ではまだ普及段階にあり、活用しているクリエイターは限られています。年齢層の高いユーザーが多いため、特定のテーマやコミュニティ運営に強い方に向いています。
Xは、近年、投稿のインプレッション数に応じた広告収益やサブスクリプション機能が始まりましたが、まだ実験的な段階で、安定収益には結びつきにくい面があります。ただし、情報発信力のあるユーザーや影響力の高いアカウントにとっては、可能性がある領域です」
最初に目指すべきは「収益化」ではない
「このようなタイプのユーザーであれば、このSNSを使うと収益を上げやすい」といった使い分け方は、あるのか。
「収益性という観点では、現時点ではYouTubeが最も安定して収益を上げやすいプラットフォームです。再生数に応じた広告収益に加え、コンテンツの寿命が長いため、長期的なストック型の収益が期待できます。一方で、短期的な拡散力を求める場合はTikTok、案件収益を狙うならInstagram、情報発信やコミュニティ形成を重視するならXやFacebookといった使い分けが有効です。
『どのSNSを使えばいいか』は、その人の強み・届けたい層・得意なコンテンツ形式によって変わります。例えば、動画編集に強い人であればYouTube、セルフプロデュースが得意な方であればInstagramやTikTokが向いています」(リデル)
もっとも、SNSで過度に大きな収益を上げようとする行為は、SNSというものが持つ性質とは相反するので注意が必要だという。
「SNSの収益化について述べましたが、そもそも各SNSプラットフォームのはじまりは、収益を目的に生まれたものではありません。自分が発信源となり、自由な表現を楽しみ、価値観の合う人やモノと出会える。そんな『つながり』や『共感』から始まったものです。だからこそ、まずは好きなことを自分らしく発信し、それを誰かとシェアして楽しむ姿勢が大切です。その積み重ねが共感や支持につながり、結果として人気や影響力という価値となって、収益化の可能性が自然と生まれていく。それが、本来あるべき健全な流れだと思います。
なので、最初に目指すべきは『収益化』ではなく、『誰かのために、楽しく発信を続けられるかどうか』です。そのうえで、より多くの人に届けるためには、SNSのアルゴリズムや、魅力的なコンテンツづくりのノウハウを学ぶことが重要です」(リデル)
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=リデル)











