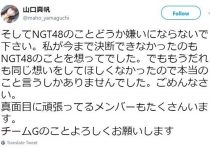強姦冤罪事件を生み出した“プロ失格”の検察と裁判所が“14歳の少女”のウソを見抜けず
 法社会学者・河合幹雄の「法“痴”国家ニッポン」
法社会学者・河合幹雄の「法“痴”国家ニッポン」第9回 2019年1月、“強姦冤罪事件”国家賠償請求を棄却、あり得ないほどの裁判の杜撰さ
強姦罪などで服役中、被害証言がウソだったと判明し、2015年の再審判決公判で無罪となった男性(75)とその妻が、国と大阪府に対して計約1億4000万円の賠償を求めた国家賠償訴訟で、大阪地裁は2019年1月8日、大阪府警・大阪地検の不十分な捜査や裁判所の誤判で損害をこうむったとする男性側の主張に対して「起訴や判決が違法だったとは認められない」とし、請求をすべて棄却しました。
この一件、ほとんどのメディアが概要を報じる程度で、ちまたでもさほど話題にはならなかったようです。しかし、メディアはこのニュースをこそ、わが国の司法の問題点を浮き彫りにしたものとして大きく取り上げるべきだと思う。おそらく司法に携わる者の多くが、私と同様に感じているはずです。冤罪事件を生み出した裁判の杜撰さと、このケースで国家賠償が認められなかったことの不当性は、専門家から見れば、それぐらいあり得ないレベルだからです。
問題について考察する前に、事件とその後の経緯を整理しておきましょう。事件が起きたのは2008年。当時65歳だった男性が、自身の養女である少女を2004年と2008年に強姦したという、少女本人の証言によって逮捕、起訴されたことに始まります。報道などによるとこの少女は、男性の妻の連れ子(女性)の娘、つまり男性にとっては孫娘に当たるのですが、2005年に男性の養女となっており、2008年の時点では14歳でした。男性は捜査や裁判で一貫して容疑を否認したものの、少女やその兄の証言が決め手となって、2011年に最高裁で懲役12年の実刑判決が確定しました。
ところが男性が服役しているさなかの2014年、少女が「証言はウソだった」と弁護士に告白、兄も証言が虚偽だったことを認めたのです。さらに、少女が事件直後に受診していた医療機関において、性的被害の痕跡がなかったことや、実際には被害を受けていないという少女の発言の記載されたカルテが存在することも判明。虚偽の証言による冤罪であったことが明白となり、男性は釈放されました。再審で男性は無罪となったとはいえ、実に6年間も不当に身柄を拘束されていたことになります。
14歳の少女のウソを見抜けない“プロ失格”の検察官
その後、男性によって提起された国家賠償請求訴訟に関する問題については次回考察するとして、今回はそもそも冤罪事件を生むに至った裁判がいかに杜撰なもので、そこに日本の刑事司法のどんな問題が隠されているかを解説したいと思います。
論点はいくつかありますが、まずは検察の問題について。ひとつはいうまでもなく、先述の通り、実は少女に性的被害がなかったことを示すカルテという客観的証拠が存在していたにもかかわらず、故意か怠慢か、検察がそれを調べようとしなかったことです。
検察はなぜ、こんな初歩的なミスを犯してしまったのか? 大阪地裁による判決文から言葉を借りるなら、「弱冠14歳の少女がありもしない強姦被害等をでっち上げるまでして養父を告訴すること自体非常に考えにくい」とはなから思い込み、少女やその兄の証言を鵜呑みにしていたからだと考えるほかありません。
報道によれば、男性の取り調べを担当した女性検察官は、被害証言の矛盾を訴える男性に対して「絶対許さない」と一切取り合わなかったそうです。性犯罪、特に被害を受けたのが子どもの場合、被害者への心からの同情と加害者への強い憤りを覚えるのが人情というものでしょう。ただしそれは、あくまでわれわれ素人の話。犯罪捜査のプロである検察官は、そういうわけにはいきません。
もちろん、検察官も人間であり、内心で何を思おうと自由です。また、刑事司法に携わる者として、被害者に寄り添おうとする姿勢も大切でしょう。ただ同時に、感情に流されず、冷静な判断と客観的な証拠に基づいて真相を見極めることが求められます。それがいまさら述べるのもバカバカしいほどの、犯罪捜査における基本であるはずです。件のカルテの存在をそもそも知らなかったのか、あるいは知りながら不利な証拠であることから隠蔽したのか、真相はわかりません。しかしいずれにせよ、少女の証言を疑おうとすらしなかった時点で、残念ながらこの検察官はプロ失格であるといわざるを得ないのです。
 「Getty Images」より
「Getty Images」より 「Getty Images」より
「Getty Images」より「有罪率99.9%以上」を支える日本の裁判所
そのような検察官に輪をかけてプロ失格というしかないのが、この事件を裁いた裁判官でしょう。私を含め多くの専門家が常々指摘していることですが、日本の刑事裁判においては、裁判官が、法に基づいて自己の判断で人間を裁くという、裁判官として本来与えられている役割を果たしていないケースが多々見受けられるのです。そして、まさにその点こそが、この事件においても冤罪を生み出す最大の要因になったと考えられます。
この事件の裁判官は、検察と同様、少女の虚偽の証言に基づく検察の描いた事件のストーリーをまったく疑うことなく、有罪判決を下してしまった。ただ、日本の刑事裁判において、これは決して珍しいことではありません。多くの裁判で、検察の主張はほぼ自動的にそのまま採用されてしまいます。よく知られた事実ですが、検察が起訴したら、裁判所はそれに対してほとんど異を唱えず、99.9%以上の率で有罪判決を下してしまうのです。
極論すれば、日本の刑事裁判で人間を裁いているのは、事実上、裁判所ではなく検察である、といういい方もできてしまうわけです。まさに今回の冤罪事件は、そうしたわが国の司法の抱える欠陥によって引き起こされたとしかいいようがありません。
「人間はウソをつく、ゆえに客観的証拠が重要」という基本
そもそも私としては、この裁判官の「14歳の少女がウソをつくとは考えにくい」という、人間に対する理解の仕方からして、首をかしげざるを得ません。皆さん、胸に手を当てて考えてほしい。人間というのがいかに簡単にウソをつき、つじつまを合わせるためにさらにウソを重ねるものであるかを。そして、子どもの頃は特にそうであることを。
もちろん多くの場合、ウソをつくのにはそれなりの理由があります。この少女にも理由はあった。先述の通り、少女の母親は男性の妻の連れ子ですが、実はこの母親が少女時代、男性と肉体関係を持っていたことが裁判の過程で明らかにされ、これについては男性も事実と認めています。そして、これはのちにわかったことですが、あるとき少女が、男性に尻を触られたことなどをこの母親に訴えたところ、母親から、おそらく母親自身の過去を踏まえて「強姦されたのでは」と強く問い詰められた。それで少女は引っ込みがつかなくなり、強姦されたとウソをついてしまった―ー。そういう複雑な事情が背景にあったようです。
大阪地裁は当初の判決文で、「(14歳の少女がウソをついて男性を告訴するというような)稀有なことがあるとすれば、よほどの特殊な事情がなければならない」とし、そのような事情は一切認められないと断じている。しかしながらこのケースにおいては、まさしくそのような“特殊な事情”があったわけです。
そういう、常識では測れないことの起こる可能性は、いかに低くてもゼロではない。だからこそ刑事裁判では、今回のケースにおけるカルテのような客観的な証拠というものが、何よりも重要な意味を持つのです。人間を裁く裁判官たる者が、そんな当たり前のことを忘れてしまったのでしょうか。裁判官が、人間はウソをつく、だから性的被害の証拠を探すべきだ、というごく基本的な思考をたどってさえいれば、冤罪は回避できたと私は思います。
次回は、この冤罪事件で国家賠償請求を認めないことの不当性と、そこから垣間見える日本の司法における人事のからんだ問題について考えてみたいと思います。
(構成=松島 拡)