
地球では過去何回も北極と南極の地磁気の逆転が起きたことが知られている。そのたびに氷河期などの気象変動が起きたとの説もある。その最後の地磁気逆転現象が起きたのは約78.1万年前とされ、その境界は2人の地球物理学者、松山基範とベルナール・ブリュンヌの名前からMatuyama/Brunhes境界(M-B境界)と呼ばれる。現在~約78.1万年前まではブリュンヌ期(正磁極)、約78.1~約258万年前までを松山期(逆磁極)と呼ぶ。
房総半島の中央、千葉県市原市を流れる養老川河岸の崖も、約78.1万年前の地球最後の地磁気逆転の痕跡が残る貴重な崖だ。その崖に露出する約78.1万前の地層が、新生代・第四紀・更新世の前期更新世と中期更新世のGSSP(国際境界模式層・点)に認められれば、その時代から約12.6万年前までが「チバニアン(千葉の時代)」と命名されることになるが、その地質学上の国際審査に、暗雲が漂っている。
最終的に国際地質科学連合が認定すれば、露頭にゴールデン・スパイク(金の杭)が打ち込まれるが、認定不可能になればライバルのイタリアの地層の時代が「イオニアン」として認定されるか、あるいは白紙となる可能性もある。ちなみに、日本で最初にM-B境界として提案されたのは京都市伏見区の大阪層群の露頭だが、その露頭はすでに削り取られている。
「チバニアン」は茨城大学、国立極地研究所など22機関32名の研究者チームが2017年6月に正式申請を行い、3段階ある審査および承認のための最終投票のうち、昨年11月に第2段階の審査が終了。現在は就活になぞらえれば「内々定」の段階で、残る3次の本審査と最終投票での「内定」を目指していた。「内定」に至る条件として、「現地への自由な立ち入りと試料採取」が保証される必要がある。決定は委員の投票で決まり、決定までのプロセスはオリンピックの開催国決定に似ているが、選定条件を記すガイドブックの基準との合致が最大の決め手となる。研究チームのリーダーである岡田誠・茨城大学理学部教授がこう語る。
「本来なら5月には第3次の申請書を出せていたので、今年の秋には決定していたはずです。第2次審査も昨年の4月には終わるはずだった。それを古関東深海盆ジオパーク認証推進協議会の方々が、いろんなメールをイタリア側研究者や国際機関に送りつけたので、それで審査が2カ月くらい中断したんです。『千葉セクションの地磁気データがねつ造されていて、地磁気の逆転が捉えられていないのではないか』という疑いをかけられたので、我々はそれに対して事実関係を説明するためのレポートを昨年5月18日に提出して、同19日に文部科学省で状況を説明する記者会見を開いたわけです。
昨年11月に終了した第2次審査では、疑義も含めて投票で決定しました。疑義自体、最初から科学的な議論ではなかったのですが、データの採り方などの状況を説明して、それが認められました。ですので、その件について国際的な学術の場での疑義はなくなりました。しかし、楡井氏はそれでもまだねつ造・改ざんだと国際機関にメールを送り続けているんです。でも、国際機関は相手にしないことを決めました。その件は問題ないと決着されているからです。それで、土地の権利を裏で獲得したということでしょう」
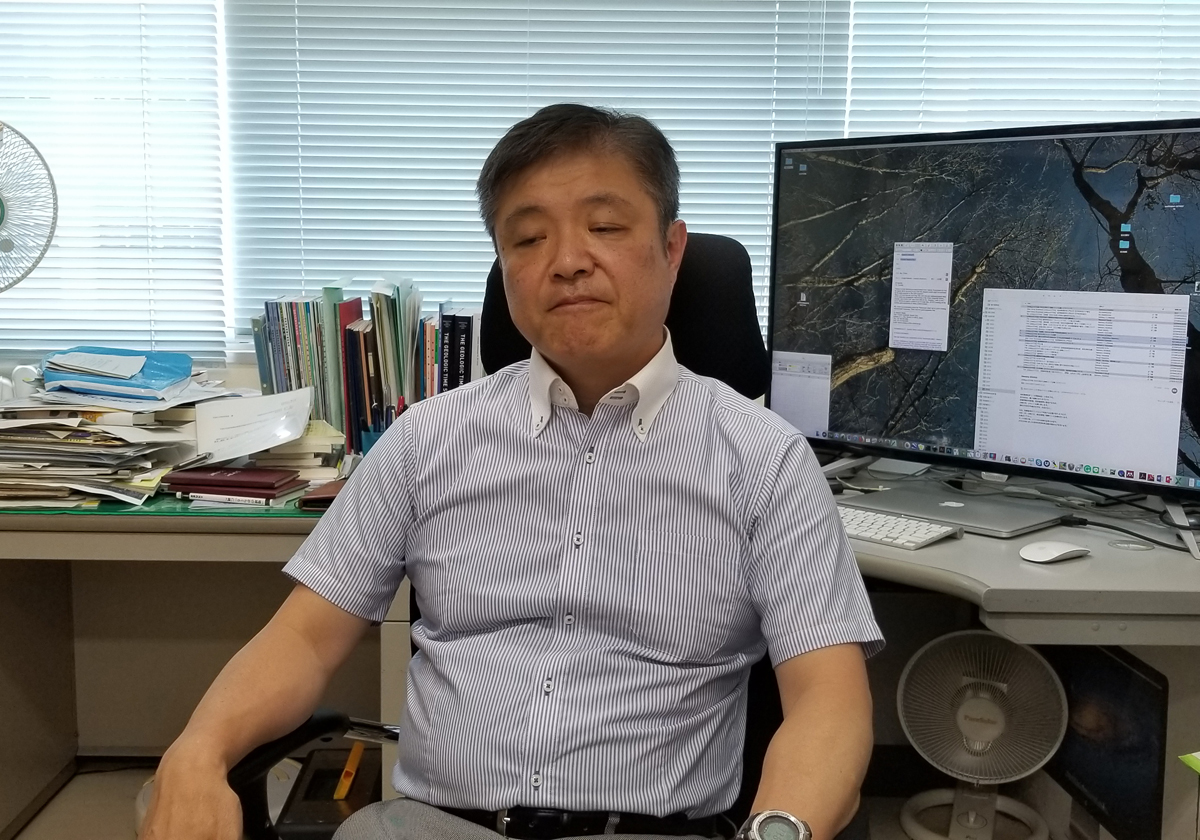
国は昨年10月に現地を天然記念物に指定し、市原市教育委員会が土地の買収を進めていたが、データのねつ造・改ざんを理由に「チバニアン」申請の取消を求める「古関東深海盆ジオパーク認証推進協議会」のメンバーが、昨年4月にイタリア側研究者や国際機関にメールを送信。これを受けて5月に「チバニアン審査中断」と新聞が報道。さらに今年5月には、昨年7月の段階で、地権者との間で月5000円の賃料で10年間の借地権を設定し、すでに登記済みであることが判明。これにより「現地への自由な立ち入りと試料採取」の保証が難しくなった。
楡井名誉教授は、なぜチバニアン申請を妨害するのか

いきなり登場して「待った」をかけ、今やすっかりチバニアン申請を妨害する悪役となった楡井氏とは、一体どんな人物なのか。
楡井久氏は1940年10月、福島県会津の生まれ。山歩きや地層などの自然観察に興味を持ち、大阪市立大学大学院で地質学を専攻。大学院修了後1970年に千葉県職員となり、30年近く地盤沈下や地質汚染、液状化などの研究に取り組んだ。県水質保全研究所・地質環境研究室長として在職中に京都大学客員教授をはじめ多くの大学の非常勤講師なども兼任し千葉県職員を退職。1998年4月から茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター教授に就任。2006年に茨城大学を退職し、NPO法人日本地質汚染審査機構理事長に就任。2009年4月に発足した「古関東深海盆ジオパーク推進協議会」の会長でもある。また、地質汚染診断士として豊洲のマンション敷地の地質汚染浄化の審査などにもかかわってきた。ジオパークは「大地の公園」のこと。日本国内には44地域あり、うち9地域がユネスコ世界ジオパークに認定されている。
この養老川河岸の田淵の露頭(千葉セクション)をGSSPに提案するための第一次調査は、すでに1991年から大阪市立大学の故市原実名誉教授、大阪市立大学の故熊井久雄名誉教授らを中心に行われており、千葉セクション開拓の先達である市原教授の愛弟子だった楡井氏も当初から調査に積極的にかかわってきた。田淵露頭の地権者や、田淵町会の人々との交渉、露頭の保存、試料採取の許可、シンポジウムなどの準備も担ってきた。91年の国際第四紀学連合北京大会では、楡井氏らが房総半島上総層群国本層の層序および古地磁気測定結果を発表。日本の房総半島はこのときはじめて、ニュージーランド、イタリアなどとともに候補地として名前があがった。
その後も、千葉セクションでは各国の研究者を招いての国際巡検が実施され、95年の国際第四紀学連合ベルリン大会のシンポジウムで、千葉セクションは熊井名誉教授らにより候補地として正式な提案がなされた。だが、国際第四紀学連合により、イタリア南部のMontalbano JonicoセクションとValle di Mancheセクション、および日本の千葉セクションの3候補地のなかからGSSPを選定する方針が正式に示されたのはようやく2006年のことである。
その前後には、新生代・第四紀・更新世の前期・中期の境界をめぐり国際機関でさまざまな議論が起こり、2004年には国際地質科学連合、国際層序委員会の層序表から「第四紀」の名称が消え、2008年の万国地質学会議オスロ大会で再び「第四紀」の名称が層序表に復活するまで混乱が続いた。同大会では候補地の予備投票も行われ、この時点で千葉セクションは第3位であった。

2010年1月、大阪市立大学の熊井久雄名誉教授より楡井氏に「このままだとGSSPは2011年の国際第四紀学連合ケープタウン大会でイタリアに決まりそうだ」との連絡が入り、楡井氏はGSSP選定に影響が強いマーチン・ヘッド教授、ブラッド・ピランズ教授を日本に招待して、千葉県市原市で行う国際シンポジウムの準備を開始した。
約1年の準備期間を経て、国際シンポジウムが2011年1月に千葉県市原市で開催された。その発表内容と現地の見学で両教授から「イタリアより千葉のほうがよいかも」との感触を得て、日本チームは新生代・第四紀・更新世の前期・中期の決定を4年先に延期するよう要請。同年12月の国際第四紀学連合ケープタウン大会で、GSSP選定が正式に4年先延ばしとなった。
2013年にリスボンで開催された国際層序委員会において、マーチン・ヘッド教授が第四紀層序小委員会の委員長に就任すると、2015年7月の国際第四紀学連合名古屋大会を目処に、GSSPの候補地選出の動きが本格的に始動した。この時点で、イタリアの2チームはGSSPの提案書に必要な準備はすでにできていたが、日本チームはまだまだ準備不足の状況であった。
マーチン・ヘッド委員長は日本側に研究チームを再編成し、2015年の名古屋大会までに必要なデータを査読つき国際誌上で発表するよう指示。これを受けて2013年10月、岡田誠茨城大学理学部教授、その教え子である菅沼悠介国立極地研究所准教授(当時は助教)らを中心とした新チームが結成された。楡井氏はその新チームによる継続調査にも、All Japanの一員として協力してきたが、それがなぜ一転して“裏切り者”となる道を選んだのだろうか。
「僕は会津出身ですから“ならぬことはならぬものです”(会津藩校日新館『什の掟(じゅうのおきて)』)で、嘘つきは嫌いです。科学の道も武士道と同じですよ。地質の時代区分の国際標準模式地は1ルートで設定するのが基本なんです。2ルートのデータを1ルートのようにしちゃダメ。日本の歴史だって1本でしょ。途中がわからないからといって、そこに中国の歴史を持ってきたらまずいでしょ。すべては2015年の夏に始まったんです」と、楡井氏は語り出した。
「2015年の夏」というのは、2015年7月27日から名古屋で開催された国際第四紀学連合第19回大会の一環として、8月3日と4日に行われた国内外の研究者やGSSPの審査委員の一部も参加した養老川河岸の千葉セクション国際巡検のことを指す。こうした巡検(現地見学)は国際大会の際の恒例行事で、しかも巡検先は更新世・前期中期境界のGSSP候補地の千葉セクションだけに大きなイベントだった。
「この巡検の場で他の場所のデータを貼り付けて説明するという科学倫理違反行為が行われました。それを国際的に明らかにしたのですが、岡田さんたちはこの『疑義』の内容について『科学倫理の問題』であるとは一言も言っていません。倫理問題のことは触れられたくないのです」(楡井氏)
養老川河岸の崖にある田淵の露頭には、古期御嶽山(現在の御嶽山ができる前にほぼ同じ場所にあった火山)が過去に噴火した際に堆積した厚さ数センチの白い白尾火山灰層(Byk-E)が1本の線として明瞭に観察できる。このあたりから下の地層が約78.1万年前より以前に地磁気が今とは逆向きになっていた痕跡が残る地層で、上の地層は地磁気が今と同じ向きになっていた痕跡が残る地層なので、その境界付近のByk-E前後で地磁気方向の移り変わりが起こった地層関係がしっかりと示されればいい。
そのためには、露頭からサンプルを採取して、地磁気が逆転していた点、地磁気が元に戻ったあとの点、そのどちらでもない中間の点、その3つが一連の地層の中で確認できることを科学的に証明する必要がある。それが証明できれば、Byk-Eから上の約12.6万年前までの更新世中期の空白の地質時代が「チバニアン」と命名される。同様の地層の候補地として、ほかにイタリアに2カ所あり、そちらに決まれば「イオニアン」と命名されるが、いずれにも決定されない場合もある。
「我々は1991年に国際第四紀学連合層序委員長のリッチモンド博士を養老川露頭へ地質案内した時から、古地磁気の逆転の移り変わりの状況を解釈抜きで、つまり古地磁気の測定データ(交流消磁法)で一目でわかるように、逆転を示した測定点を赤い札などで表示してきました。2015年の時も同じように色別の杭を試料採取孔に打ち込んで示すために、岡田教授に計測済みの古地磁気データを提供してもらいました。データは表としてのみメールで来たのですが、なんか変な文面だったんですよ。『田淵ではByk-Eより50cm上位までしか測っていませんが、ダミーの孔を開けてあるのでyanagawaのデータを使って極性の色をつけてください』というものでした。それが6月22日です。
学生を指導する大学教授がねつ造をあからさまに指示するとは考えられず、当時すでに古地磁気の試料採取孔は空いていたので、巡検当日には古地磁気測定用に採取した孔の測定データを説明するはずと思い、メールの指示に従い色テープを試料採取孔の横に貼りました。地磁気の逆磁極データは赤、正磁極データは緑、中間データは黄色のテープです。それを貼ったのが2015年6月26日で、指示通りに色別表示杭を試料採取孔に打ち込んだのは7月23日でした。大会が始まると私も名古屋の会場に行って、露頭全体が写った写真を見せて色別表示杭について菅沼助教に確認してもらったところ、一部の杭の色の変更を指示されたのです。それが7月29日でした。
田淵の露頭現場では、その指示通りに杭を打つことを再確認し、打ち直す前に確認のため岡田教授の携帯に電話したのですが繋がらなかった。それで、名古屋会場の菅沼助教の携帯に電話して確認したところ、『29日の指示通りで問題ない。岡田教授と確認もとれている』とのことでした。それで我々は7月30日夕刻、菅沼助教の指示通り露頭に色別の表示杭を打ち直しました。その送られてきたデータがまさか田淵から1.7キロ離れた柳川セクションのデータを含んでいたとは思いもしませんでした。結果的に色別表示杭はきれいに下から赤、黄、緑の順番に並んだのです」(楡井氏)

データのねつ造・改ざんを疑うようになった経緯
8月4日の巡検では、楡井氏らが打ち込んだ色別表示杭を使って菅沼・岡田氏らが説明を行ったが、楡井氏はその際、参加していた国内の古地磁気専門家が「この3色一列は下から順にきれいに合わせてしまったのでは?」と日本語でつぶやいた声を耳にして、これはデータの改ざんが行われたのではないかと疑い、8月15日、日本側の国際層序委員だった大阪市立大学の熊井久雄名誉教授に報告した。その結果、8月24日、立川の国立極地研究所に国際巡検の主要メンバーを招集し聞き取り調査が行われ、楡井氏はそこで初めて、柳川セクションのデータが貼り付けられたことを知った。それで、古地磁気データ表示の指示の中にねつ造と改ざんの両者が含まれていたことを認識したという。
その会合には審査委員会である第四紀層序小委員会の委員長で、カナダ州立ブロック大学のマーチン・ヘッド教授も同席していた。岡田、菅沼両氏や学術会議関係者を含む参加者は以下の2点について合意した。
(1)岡田、菅沼両者が田淵露頭での古地磁気測定結果の説明の際、露頭での色別杭による極性表示において、上部の未測定部分にほかの露頭(柳川)での測定データを貼り付けたものであったこと、そしてその点を説明せず、データ全部が田淵露頭からのものであると参加者に説明したことを、この国際巡検の報告とともに国際第四紀学連合のニュース紙に投稿する。
(2)岡田、菅沼両者はByk-Eの上位55cmから上について田淵露頭で再度試料を採取し測定し直す。
上記2つの合意内容については、熊井久雄名誉教授が同席したマーチン・ヘッド教授に示し、ヘッド教授も含めた合意だったという。岡田教授になぜ未測定だったのかを聞いた。
「2015年8月は、Byk-Eの上位50㎝付近までは田淵でやったんですが、田淵は露頭の高さが限られていたので、そこから上6mまでは柳川を使いました。サンプリングしたのは2013年ですが、一通りデータも測って論文も書いたのです。その後、2014年の夏にジオパーク側の人に言われて、現地でも説明があるから試料を採取しておいたほうがいいというのでサンプリングはしたんですが、その測定は我々の中での優先順位が低かったんです。すでにM-B境界の地磁気データが出ている状態で、論文も投稿間際でした。私もGSSPの申請なんて初めてのことですし、申請書作成のため提出が必要なデータが他にたくさんあったからです。
有孔虫という1㎜以下の原生生物の死骸の微化石の酸素同位体比データを詳細に出すことが申請には必須だったのですが、有孔虫の殻は0.1㎜と小さく、岩石から取り出すのにものすごく時間かがかかるので、それを優先したんです。それで、地磁気測定用に採った試料をしばらく湿った状態で放置してしまったのです。湿った状態で放置すると風化して茶色く変色してしまいます。数カ月後に見ると完全に変色しており、同じ条件で磁化成分を取り出すことができないため測るのをやめたんです。それでデータが出ずに残った孔を『ダミー』と称してしまったんですが、誤解を与える表現でした。その後、2015年の秋から2016年にかけて田淵の壁面全域を含め、さらに広範囲で再サンプリングして、より優れた手法(熱消磁法と交流消磁法)で古地磁気測定を行いました。その結果を、私が論文を書いて投稿しています」
これに対し、楡井氏はこう反論する。
「千葉セクションで最初に試料採取の孔を開けたのは2013年9月13日です。そのときはByk-Eの上45㎝から下方に向けてで、その後、2015年2月28日に今度はByk-Eの上55㎝から上方に向けて追加で試料採取されたのを確認しています。それなのに、なぜGSSP申請予定の試料を測定していないのか。サンプルを採取したらすぐ測定するのが当然ですよね。なぜ半年以上も測定しなかったんでしょうか? 実質的には前年イタリアで行われたGSSPの国際巡検を受けての巡検だったので、古地磁気の測定結果を現地巡検参加者に分かり易くするために色別の杭表示をしようというのは、2015年春のAII Japanの研究者会議の時に全員合意しています。
岡田教授たちは、論文を基に杭の打ち直しを指示したと言っているのですが、その論文が田淵のデータでない部分を含んでいたんです。異なる場所のデータの貼り付けを指示し、それを用いてこの場所のデータとして説明した事実は、どのような言い訳をしても消えません。倫理問題に触れたしっかりした謝罪も反省もありませんでした。これでは科学者としての資格が無いのではないでしょうか? 論文には柳川だと書いてあると言いますが、そのデータは主論文にはなく、インターネットからアペンディックス(付録)を探さないと見られないものだったのです」
岡田教授はこう説明する。
「2015年の2月2日の全体会議では、田淵の露頭で(杭を含む)表示をしない事で楡井氏を含めチーム内で合意していました。その後、4月13日と5月26日に全体会議を行いましたが、杭表示の話は一切出ていません。議事録はその都度チーム全員に配信していますので、これはチームとしての共有事項です。ところが、6月になり楡井氏のほうから色で識別した杭を打ちたいと突然言ってきたんです。そこで当時の最新論文で公表されていたデータをメールで送りました。論文では付録の図でデータ採取場所も全て公表されているので、当然どのデータが柳川だとも書いてあるんです。
それらはネット経由で世界中からアクセス可能です。それで、データがねつ造だとか言われても、論文に書いてあるとしか言いようがないんです。彼らの作業工程上、孔の縁に最初に渡したデータを基に色別テープを貼っていたみたいです。しかし、彼らが用意した説明文がデータ説明としては不正確だったので、そのあとで私と菅沼さんで話して、菅沼さんの論文での記述に従って色付けをしてくださいと頼み直したんです。
メールで『はい、わかりました』と返ってきたので、そうなっているのかと思ったら元のままの杭の配列だったので、打ち直してもらったら、それが改ざんだと言っているんです。誰かがデータを改ざんしたみたいに表現しているんですが、それは僕らが『論文記述に従って打ち直してください』と頼んだからです。論文記述に沿うよう修正をお願いしたことを『改ざん』と主張し続けているんですよ。とにかく、楡井氏は2015年の夏の段階で全てが固定されて、それ以上の事実を頭に入れないようにしているんです」
そう、この騒動は「2015年の夏」をめぐる騒動なのである。2015年8月4日の国際巡検の際、色別識別杭で表示した千葉セクションのデータは、Byk-Eの上50㎝以上は未測定だった。その部分のデータとして提供されたのは、田淵から1.7㎞先にある柳川セクションのデータだった。そして、論文に書かれていたとはいえ、その事実を国際巡検の参加者たちに説明せず、あたかも田淵のデータであるかのように説明してしまったこと。それは科学倫理に照らしてアウトなのかセーフなのか? それがチバニアン騒動のすべてである。
楡井氏の判定はその時点ですでに「アウト」。ゆえに、その後の再測定でどんなデータが出ようと、それは認められないというものだ。
一方の岡田教授の判定は、現場で説明しなかったのは事実だが、それについても修正説明をしているので「セーフ」。その後、新たに試料を採取して再測定を行ったうえ、その論文も2017年に提出している。さらに、巡検とGSSP申請には直接の関係はない。したがって、GSSP申請に何ら問題はないというものだ。
なぜ地権者に無許可で試料採取したのか

楡井氏の主張はこうだ。
「昨年6月に無許可での大規模盗掘が発覚したんです。盗掘した試料から得られたデータなんて絶対に認められませんよ。科学者なのに、なぜそんなこともわからないのか。市原市の許可を得たと言うけれど、地権者でもない市原市がなぜ許可できるんですか。彼らは試料採取計画がずさんだったんじゃないでしょうか。国際巡検の後、千葉セクションから60m離れた養老-田淵セクションで試料を採取し、測定したら古地磁気のいいデータが取れた。もう柳川セクションのデータは必要なくなったんですが、養老-田淵のデータはByk-Eの上2mから始まり、この上部しか測定していなかった。地磁気の極性が変わる肝心な部分の連続的な測定が一つの露頭で行われていないことを、イタリアチームか審査委員側に岡田氏たちはつつかれたのでしょう。だから、彼らはどうしても試料を採取して測定する必要があった。盗掘現場の写真ともぴったり一致します。実はイタリアの候補地の一つも地層ルートは複数。日本のルートも複数なのでそこを突かれたんだと思います」
岡田教授の説明はこうだ。
「昨年5月下旬に現地でサンプリングしたのは、千葉セクションから60m離れた隣接する沢です。Byk-Eの上2mから上位のデータはすでに得られていました。1次審査の時に、両セクションの間に不連続があるのではないかという質問がきていたので、2次審査ではその質問に答える必要がありました。そこで隣接する沢でByk-Eの所から新たにデータをとり、両者の間をオーバーラップさせることで不連続がないことを示したのです。試料を採取する際、市原市に『権利上、問題のないところで採取したい』とお願いしたところ、『市が管理する水路部分なら問題ないです』というので、市の職員の同行のもとで採取したのですが、あとから民有地に入っていたことがわかり、市も私も地権者に謝罪しています」
楡井氏が借地権を設定した理由
「市原市の天然記念物の委員会の委員長は岡田教授ですからね。市のものになれば、自分のごまかしを消せるわけです。それまで、我々は地元の方々と仲良くやってきて、試料採取や管理も従来からの地権者との協力関係から、我々が地権者の許可を得るかたちでやってきたんです。自然の流れとして、それまで暗黙の了解であった土地の利用に関しても、地権者と私たちとの間で文書化することになりました。昨年7月に賃借料も支払うことになりました。このことは、その後の経過を見ると、ねつ造・改ざんの証拠の隠滅を防ぐことに役立っています。そういうごまかしの証拠隠滅を防ぎ、今後の科学のねつ造・改ざんの予防のための反面教師として、国民に知らせることが重要と考えています。広島の原爆ドームを残すのと同じです。“ごまかしの壁”でも、“データ改ざんの壁”でもいいので、現場を残したかった。ちなみに、現在も一般見学者の立ち入りは自由です。
私は、GSSPにも係わる基礎地質学のほかに地震時の液状化、人工地層、地質汚染科学の研究が専門なので、ねつ造とか改ざんは困るのです。現地で真剣に議論するときに地層データの貼り付けが許されたら、建築や土木の構造物を作る関係業界、高レベル処分場の立地の検討、汚染された土地・地下水・地質の浄化、ましてやそれらを生活に使う国民は大変な迷惑ですよ。それもあって妥協できないんです。我々に無許可で行った試料の盗掘も警察に届けてあります。無許可で取ったサンプルのデータは科学的に認められませんからね。この実態は海外にも全部知らせている。それなのに、気付かない振りをしている日本地質学会も地球電磁気・地球惑星圏学会もみんな熱に浮かされているとしか思えない。日本学術会議も自浄作用が欠如しているのではないですか」(楡井氏)
岡田教授はどうしてこんなことになったのか、首をかしげる。
「なぜこうなったのか、根が深いんだと思います。楡井氏にとって、GSSPの話もジオパークに利用できる駒のひとつだったんでしょうね。自分がその権益を確保したかったが、天然記念物になると市原市のものになってしまうので、それをなんとしても潰したいんでしょう。2016年の3月か4月から明確に方針転換がはじまって、それから妨害活動を開始してきたんですが、僕らは何もわかっていなかったんです。
楡井氏からは『地元の人が怒っているから現場には近づくな』とずっと言われていたんです。2016年10月までは、地元と我々とのやりとりは、楡井氏を仲介するよう命じられていたのですが、これも後から考えればおかしな話です。その後、市原市を介して田淵町会の方々と初めて接触したら、GSSP申請に反対している方は一人もいないことがわかったのです。こんなことのために試料採取が半年滞り、申請準備が大きく阻害されてしまった。これらも妨害活動の一環だったんだと、私たちは後になってようやくわかったんです」(岡田氏)
チバニアンの地元である田淵町会(130世帯)の住民は今回の騒動をどう見ているのか。
なかには「科学的な決着をつけてほしい」と、楡井氏に賛同する住民もいるという。そこで町会の広報担当者に話を聞いた。
「町会全体で楡井先生に協力していたというより、そのときどきの役員や町会長が個人的に協力していたようです。古い方たちは楡井先生に対して、あの人があれだけ反対するんだから、何か理由があるはずだと思っている人もいます。でも、岡田先生に初めてお会いしたとき、『地元には近づくな』と楡井先生に言われていたと聞いて驚きました。田淵町会はチバニアンを認定してほしいという立場なので、今は楡井先生のグループとは一線を画している状態です。
土地に関してもチバニアンではなく、天然記念物に指定されたことに伴う買収で、町会に住む地権者で反対している人はひとりもいません。現在は役員会で最新の声明文を出したばかりです。田淵町会はチバニアンの認定が3次審査できちんとした学問的な評価を受けて通過することを強く望んでおり、関係各位にはそのための協力をお願いしたいというものです」
この問題はどこへ向かおうとしているのか
岡田教授は昨年11月の2次審査の投票結果が、22人中賛成が19票だったこともあり、科学的疑義はすでに晴れていると主張。一方の楡井氏はねつ造、改ざん、盗掘は事実との態度を崩さない。いずれにしろ、ここまで来ると両者の歩み寄りは難しそうだ。今後はどうなるのか。両者の見解を聞いた。
「このままだと世界の地質学に迷惑がかかります。千葉県だって迷惑ですよ。科学者は正直でないとダメです。それが成果主義で変わってしまった。本当のことを言えば、僕だってずっとやってきたわけだから、本音はGSSPが欲しかった。でも、嘘までついたらダメだと言うことです。科学の道は厳しいものです。いつの間にか科学倫理の話が不動産の話になっているわけです。責任をすべて僕にかぶせて白紙にするシナリオかもしれないですね。その可能性もあります。市原市の小出市長には、私もすでに手紙を書いて出しましたが、市原市という行政機構を巻き込んで、強引にGSSP審査を押し通そうとする姿勢は批判されるべきだと思います」(楡井氏)
「勘違いと思い込みによる『ねつ造・改ざん』主張も含め、今後、関連学会や国際機関が相手にすることはありません。それでもアクセスの自由が保証されないと申請できないのです。今は市原市がいろいろ工夫して探っているところなので、とにかく『自由な立ち入りと試料採取』が保証された申請書を今年の9月までに出したい。小出市長のもと、市原市がやってくれると信じています」(岡田教授)
先月24日、さっそく動きがあった。市原市の小出譲治市長が緊急記者会見を行い、土地の所有者や賃借権者らに対し、正当な理由なく研究者の立ち入りを妨げてはならないことを定める条例の制定を目指す考えを示したのである。会見で示されたのは(1)天然記念物に指定された地層の保存と活用(見学等)のための保存活用計画と整備基本計画の策定、(2)一般の見学者向けにパネルや映像を使った解説を行う仮設ガイダンス施設の建設、(3)国内外の研究者の要望に応えるため、現地への立ち入りを保証する条例の制定、の3つである。
天然記念物に指定された土地は36区画で計2万8500平米(約8636坪)だが、楡井氏が賃借権を登記した土地はそのうちの155平米(約47坪)。制定を目指す市原市の条例は地層全体の2万8500平米がその対象となる。条例が制定されても、賃借権を登記された土地での試料採取はNGだが、そこを通らないと行けない別の場所での研究や試料採取が目的であれば、条例で通行権を保証しようというのが狙いだ。
この条例制定が解決策となることを望みたいが、今後は法律論議に発展する可能性もゼロとは言い切れない。長らく傍観者だった市原市が、ようやくチバニアン推進に向けて舵を切ったことで、これまで楡井氏が突きつけていた矛先が、今度は市原市にも向けられることになる。事態の収拾までにはまだひと波乱もふた波乱もありそうだ。また、あの夏から4年目の夏が巡ってくる。
(文=兜森衛)




















