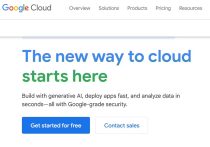バイブコーディングの理想と現実…効率向上には、やっぱりプログラミングのスキルが必要?

●この記事のポイント
・生成AIにプログラムのコーディングを任せるバイブコーディングの利用が広がっている
・人間が適切なプロンプトを書けるかどうかが重要なので、スキルがない人では難しい
・AIエージェントを使うことは開発の現場ではすでに当たり前に。いきなり完成形を目指さない
生成AIにプログラムのコーディングを任せるバイブコーディングの利用が広がっている。より高度な機能を持つAIコーディングツール、AIコーディングアシスタントなども含めると、米OpenAIの「Codex」、米Anthropic(アンソロピック)の「Claude Opus 4」、米グーグルの「Jules」など有力テックも開発に力を入れている。米メタや米マイクロソフトもすでに自社の開発にAIコーディングを取り入れているという。大幅な開発効率向上や開発要員を確保するコストの削減、プログラミングのスキルがない人でもコーディングができるようになるといったメリットがあると期待が高まる一方、こうした効果に否定的な見方も少なくない。果たしてバイブコーディングを使うと、大幅に開発効率が向上するなどのメリットが生じるのか。逆にデメリットや“陥りやすい罠”などはあるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
●目次
適切なプロンプトを書けるかどうかが重要
「以前からあるエディターに組み込まれたサジェスト機能を使うパターンは自分でコーディングを行う作業の延長線上なので、それを除くと、バイブコーディングというのは、人間がプロンプトである程度命令を出して放置していたら、自動的にタスクが出来上がるというものを指すのだと思います。結論からいうと、現時点ではまだバイブコーディングの精度は低いというのが正直な感想です。いかに人間が命令を具体的に書くかで結果が大きく変わってくるので、『どこまで精密さを求めるのか』『どのくらい妥協するのか』といった感覚が重要になってきます」
こう解説するのは株式会社ディーゼロ執行役員でウェブアクセシビリティスペシャリストの平尾優典氏だ。プログラミングのスキルがない人がテキストで指示するとプログラムが出来上がるという単純は話ではないということか。
「例えばプログラミングの知識がない人でも、システムの完成形を正確にイメージできていれば、たとえAIが生成したコードが間違っていたとしても、ツールとのやりとりのラリーを重ねることで“その人にとっては”システムがつくれたということになるかもしれません。ですがプロのエンジニアがつくるプログラムは書き捨てることはほとんどなく、完成した後にメンテナンスや機能拡張をしていくので、『こういうコーディングだと、のちのち拡張ができない』といったことを意識しながら開発をしていきます。また、システムは一つの入力に対して一つの結果しか返さないというわけではなく、さまざまな入力パターンに対して正しい結果を返す必要があるので、『こういう入力パターンだと正常に作動しないのではないか』『つじつまが合わない結果を返してしまうのではないか』といったことを考えながらコーディングしていきます。
そうしたパターンやパラメーターをより多く想像できるのがプロのエンジニアなのですが、そこにAIがついてこれているかというと、あまりついてこれていません。精度が高いシステムをつくるには、人間が適切なプロンプトを書けるかどうかが重要になってきますが、そこはスキルがない人では難しいでしょう」(平尾氏)
単純に人間よりAIのほうが安いとはいいきれない面も
バイブコーディングを使うことによって、コーディングの効率は向上するのか。
「効率は向上するとは思いますが、AIエージェントのモデルによって性質が変わってくるので、どのようにプロンプトを書けばよいのかというスキルを身につける必要があります。また、モデルの性能は日進月歩しているので、昨日はできた方法が今日は使えなくなっているということも珍しくなく、こういう状況が果たして効率向上につながるのかどうかという疑問も感じています。
AIコーディングツールは、知識はあるけど経験は浅い新卒社員に似ていて、部分的な知識は豊富だけれども組み合わせ方が未熟という表現が近いかもしれません。人間だとレビュアーがレビューをしてシステムを完成させていくという進め方になりますが、AIコーディングツールも同じようなことをする必要があると思います。新卒社員を雇うよりもAIにコーディングさせて人間がレビューするという進め方のほうが効率的に思えるかもしれませんが、長期的に見ると新卒社員は育っていくのに対し、AIは自律的に育っていくわけではないので、単純にAIのほうが安いとはいえません。
ただ、コスト的には人間よりAIのほうが圧倒的に安いので、『この業務はAIでできるのではないか』と新しい人を雇うことをためらったり、相当優秀な人じゃないと採用しないという動きは、企業の間では広がっていると思います」
では、バイブコーディングが近いうちに日本で普及する可能性はあると考えられるのか。
「AIエージェントを使うことは、開発の現場ではすでに当たり前になっています。ただ、全面的に使うというわけではなく、例えば8割方はバイブコーディングでつくって、残り2割は人間が修正していくといった感じなので、いきなり完成を目指さないというのが、うまく付き合う方法なのかなというのが現段階での感覚です。
個人的にはプロンプト一発でAIがタスクを自動的に完了までやってくれるというのが理想的ですが、現実的には人間が逐一、ギチギチに指示書を書いて、それをAIに読ませながら手順をしっかり守ってやらせるというかたちになっています。バイブコーディングはルーティンタスクの実行はとても不得意なのですが、私としては自動的にAIにやってほしいというのがあり、ルーティンタスクはある程度手順も決まっているのでAI的な推論を期待する部分ではあるので、MCPサーバーを使ったりして工夫しながらやっているところです」
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=平尾優典/ディーゼロ執行役員)