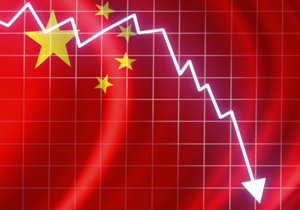 「Thinkstock」より
「Thinkstock」よりリーマンショックならぬ“上海ショック”が世界の株式市場の動揺を招いている。中国がくしゃみをすると、全世界が風邪を引きかねない構図が垣間見える。
これまでも中国経済の下振れ懸念は不安視されていた。今年7月15日に公表された中国の4~6月期実質GDP成長率は前年同期比プラス7.0%となり、かろうじて7%台を死守した。日本の同期のそれがマイナス0.4%であるのと比較すれば、格段に高い水準ではあるが、世界経済の成長エンジン(牽引役)として2ケタ成長してきた過去の水準と比べると、成長の失速は否めない。
こうした景気に対する悲観論の高まりを受け、中国の株価は下落局面へと突入した。上海総合指数は6月12日の5166ポイントをピークに、7月初旬には3割以上も急落した。1日で4%以上も下落する日もあり、手のひらを返したような暗転相場となった。そこで中国政府は株価対策に乗り出し、公的資本の市場投入や信用取引に関する規制緩和、さらに新規上場株式に対する承認の一時停止など、暴落する株価の下支えに躍起となった。
しかし、それでも反転上昇とはならず、引き続き下値を探る展開となった。そのため、8月11日には人民元の切り下げを実施し、元相場を大幅に安値誘導することで輸出促進による景気の下支えを目指そうという異例の措置に打って出た。
にもかかわらず効果は限定的で、株価への下押し圧力は強まるばかりだった。株安の連鎖は日本にも伝播し、日経平均株価は8月18日から6営業日連続で下落した。この間の値下がり幅は2800円余りとなり、あっさり1万8000円台を割り込んでしまった。米ニューヨーク株式市場ではダウ平均が週末の21日・週明けの24日と2日続けて500ドル以上も値下がりした。同時にユーロ圏にも不安の連鎖は飛び火し、中国経済の減速を背景とした「世界同時株安」が現実のものとなった。
慌てた中国政府は8月26日に追加の金融緩和を実施し、以後、一定の歯止め効果は出ているが、警戒感の払拭までには至っていない。依然、中国政府に対する不信感が根強く残っているからだ。いまだ混乱収束への不透明感はなくならない。
上海ショックに過剰反応する必要はないが、軽視するのも危険だ。08年9月に米証券業界4位のリーマン・ブラザーズが経営破綻し、世界金融危機のリーマンショックが勃発したとき、日本の市場関係者は「海の向こう、アメリカの話。日本の金融市場ならまだしも、日本の実体経済にまで影響を及ぼす心配はない」と誰もが楽観視していた。





















