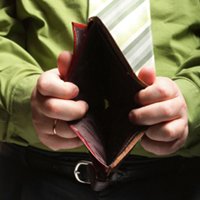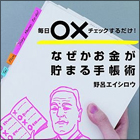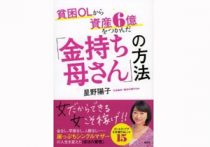日本銀行本店(「Wikipedia」より/Wiiii)
日本銀行本店(「Wikipedia」より/Wiiii)例えば、将来を考えて自宅をバリアフリー化しようとした場合、建設コストが将来的に割高になると予想すれば、貯蓄を減らしてなるべく早めに工事を発注するだろう。これに対して、建設コストが割安になると予想される場合には、何も今すぐバリアフリー工事が必要というわけではないので、とりあえず本当に困るまで工事は延期しようという話になる。
これは家電製品や自動車の購入でもまったく同じだ。人々はそれぞれが持つ「感覚」によって微妙なシグナルを感じ取り、将来的な経済状態を予想する。そのシグナルとは、例えば「同業他社が突如として銀行借り入れを増やし、設備投資を始めた」とか、「隣の住人が今年は頻繁に海外旅行に出かけていることを、お土産で気付く」とか、「親戚が住宅ローン破綻した」とか極めて些細な出来事だ。
優秀な経営者はシグナルを捉える名人でもある。逆に、無能な経営者はノイズをシグナルと見間違える。1989年に日経平均が3万9800円台のピークを付けた後、90年に1万円以上暴落した。これを一時的な調整と見るのか、長期的な暴落と見るのか、それが運命の分かれ道だった。
50年代のアメリカは空前の消費ブームに突入した。これを一時的なものと見なし、いずれまた世界恐慌のようなデフレになると考えた企業があった。カタログショッピングという手法を世界で初めてつくり上げたモンゴメリーワードという百貨店である。投資をケチって内部留保を積み上げた結果、銀行借り入れを増やして大都市周辺地域まで積極的に進出した後発組のメイシーズなどに追い抜かされた。そして、最盛期250店舗を誇った店舗網は30店舗まで縮小し、いまから14年前に倒産してしまった。
なぜ50年代のアメリカで人々は貯蓄を減らして消費を増やしたのか、そして90年代の日本で人々はなぜ消費を減らして貯蓄を増やしたのか? そもそも、人々が貯蓄率を変化させる原因となる期待は、なぜ生じるのだろうか? 将来的にモノが不足すると考えるインフレ期待も、その反対のデフレ期待も、人々がそう期待するからには何か根拠がある。人々が「シグナル」として捉えたものが発生した根本の原因を探るために、実は経済学はとても役に立つ。
政策の「レジーム転換」が「期待の転換」をもたらす
経済学の知見によれば、人々の「期待の転換」をもたらしたのは政策の「レジーム転換」である。89年1月、日本銀行はすでに史上空前の低金利となっていた公定歩合を将来的に引き上げる引き締め政策に転換した。翌年には公定歩合は6%まで急激に引き上げられたのだ。最初に反応したのは株式市場である。将来的な資金調達コストの上昇を見込んで、企業業績が悪化すると予想したのだ。次に反応したのは土地価格である。91年をピークに地価の値下がりが始まった。95年には住専問題が発覚し、それが97年から98年にかけての金融機関の相次ぐ破綻へとつながり、多くの国民がこの時やっと日本経済に異変が起こっていることに気づいた。目端の利く人は、89年1月の日銀の政策変更を見逃さなかっただろう。しかし、大抵の人はボヤボヤしていたのだ。
50年代のアメリカにおける消費ブームも、まったく同じだ。第2次世界大戦の終結によって、戦時統制が終わり、人々が我慢していた欲求を爆発させた。旺盛な需要に対して供給が不足している。しかも、戦後アメリカはブレトンウッズ体制を築き上げ、ドルを基軸通貨に据えた。世界中にドルを供給するためにはFRB(米連邦準備理事会)が今まで以上にたくさんのドルを刷らなければならない。これは緩和的な金融政策を意味する。このように、金融政策の「レジーム転換」は、良い方向にも悪い方向にも、人々の将来的な期待を変更させる。
では、アベノミクスが日本経済に与えた期待の転換は、「90年代日本型」と「50年代アメリカ型」のどちらの類型に当てはまるであろうか? 「黒田バズーカ」と呼ばれる黒田東彦日銀総裁による大胆な金融緩和政策は、「マネタリーベース(日銀から市場への資金供給量)を2年で2倍に増やす」ことを目標にしている。どちらの類型に当てはまるか、誰でも考えればすぐにわかるはずだ。
ところが、世の中にはシグナルとノイズの見分けがつかない人がいる。まして、そういう人が経済評論家やエコノミストを名乗っているから始末に負えない。彼らは安倍政権と黒田日銀が起こした金融政策の「レジーム転換」という大きな出来事から目を背け、些細なことに執着し、人々に誤った情報を伝えている。しかも、彼らの主張は出典を確認できなかったり、計算根拠やデータを示さないために検算ができなかったり、穴だらけだ。そんな「創作経済学」を鵜呑みにしてしまうと、当然のことながら将来的な判断を誤ってしまう可能性が高い。悪徳商法の被害拡大を防止するのと同じ倫理観において、「創作経済学」を見分けるために必要な典型的な間違いを3つ指摘する。
・典型的な間違い(1):自由貿易をするとデフレになる
すでに確認した通り、将来的なインフレ期待、デフレ期待は金融政策のスタンスによって決定される。自由貿易体制への移行が金融政策のスタンスの変更につながる場合は、影響があるかもしれない。例えば、固定相場制から変動相場制への移行といった制度変更はこれに該当するだろう。
では、戦後日本が固定相場だった71年までの状況を見てみよう。戦後、日本は一貫して自由貿易を進めてきた。この間、一度でも日本がデフレに陥ったことはあっただろうか? むしろ、この時代はインフレをどう抑えるかのほうが問題だったのではないだろうか。つまり、自由貿易を推進してもデフレがどころかその反対のインフレが発生していることから考えて、「創作経済学」は現実を何も説明していないことがわかる。
さらに、次のグラフを見てほしい。第2次世界大戦終結後、全世界が自由貿易体制を推進してきた。「自由貿易をするとデフレになる」という主張が正しいとすると、これほど大規模な自由貿易体制が推進されたのなら、世界中がデフレになっているはずだが、現実はまったく逆である。
日本が変動相場制に移行した1971年以降で見ても、一時的な物価下落はあったとしても、それが2年以上継続して続くデフレ状態になったのは日本だけである。その理由は日銀が98年からずっと引き締め気味の金融政策を続けていたからだ。
・典型的な間違い(2):公共事業でデフレ脱却
公共事業万能論という誤った考え方がある。これはデフレも景気の低迷も公共事業を増額すればすべて解決できるというものだ。公共事業は財政政策の一種であり、日本のような変動相場制の国では金融緩和と同時に行えば一定の効果を発揮する。現在、アベノミクス1本目の矢である金融緩和が効いている状況にあるので、本来公共事業は景気に対する好影響を与えるはずだった。
ところが、ここへきて建設業全体の供給能力が大幅に減少していることが明らかになった。その理由は、長引くデフレと予算削減によって、建設会社や下請け企業が大幅なリストラを実行したためである。10年以上かけて削減してきた人的リソースを数年で取り戻すことは不可能だ。全国各地で起こっている公共事業の入札不調は、まさにこの状況を反映している。
また、現場に熟練工が不足しており、施工不良による工事のやり直しといった初歩的なミスも多発している。その最も典型的な事件は、東京・青山の「億ション工事失敗事件」だ(http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20140203/382305/?ST=safety)。
中学校の社会科で習ったケインズの自動安定化装置(ビルトインスタビライザー)の発想においては、「民間の需要が旺盛の時、政府は支出を抑制して財政健全化に努め、逆に民間需要が低迷した時、政府は公共事業などによって景気を刺激する」ことになっていたはずだ。金融政策の劇的なレジーム転換によって民間需要は旺盛となり、すでに建設業の供給能力は限界を迎えている。それでも公共事業が必要なのだろうか? 民需旺盛の今、公共事業をさらに推進しようというのはケインジアンを自称する「似非ケインジアン」の所業である。
仮に、強引に公共事業を推進したとしよう。政府と民間が建設業のリソースを奪い合い、価格は高騰する。景気が良くなってきたので、店舗を改装したり、設備を増強して売り上げを増やそうとした経営者にとってこれは悪夢だ。去年は1000万円でできた工事が、今年は3000万円に値上がりといった事態になると、結局投資そのものをあきらめてしまうことになりかねない。民間の投資がしぼんでしまえば景気は低迷する。景気が低迷すれば税収は減り、結局、公共事業の支出も維持できなくなる。最終的に民需低迷の後、官需が低迷し、共倒れとなるのだ。無理やり官需を維持するために増税すれば、ますます民需は低迷し、悪循環に陥る。「津波で1人も死なない」といった過剰な安全神話を煽って公共事業万能論を吹聴する人々は、経済停滞によって日本国民全員を奈落の底に突き落としたいのだろうか。
・典型的な間違い(3):外国人労働者が流入するとデフレになる
物事を単純化して説明する場合には、単純化しても本来説明すべきエッセンスが抜けてしまわないように細心の注意を払う必要がある。しかし、エッセンスが抜けきって、もはや原形をとどめていないような単純化が独り歩きしているケースがある。あらゆる経済政策を「インフレ政策」「デフレ政策」の2つのカテゴリーに単純に分けて、「デフレの時にデフレ政策をやるとデフレを助長する」と主張する人がいる。問題は何を基準として「インフレ政策」「デフレ政策」と分類するのかという点である。この手の主張には、大抵「価格」と「物価」の違いが抜け落ちている。「価格」とは個別のモノの値段(相対価格)のことである。これに対して「物価」は、あらゆるモノの値段の加重平均(一般物価)である。
外国人労働者を安い賃金で使うことができれば、確かに名目賃金は下がるだろう。しかし、企業はそのことによって節減した経費を一体どうするだろうか。そもそも、外国人労働者を使わざるを得ない状況にあるという時点で、人手不足が深刻化している。なぜ人手不足になっているかというと、前述の通り建設需要が官民ともに高まり、それに供給力が追い付かない状況にあるからだ。もし筆者が企業経営者なら、外国人労働者を使って浮いたお金を建設機械やより多くの労働者の採用に投資し、より多くの仕事を受注しようとするだろう。なぜなら、少なくとも6年後の東京五輪までの間は、仕事がたくさんあると予想するからである。
では、企業経営者が浮いたお金を全額再投資する限りにおいて、なぜ「デフレ期待」が発生するのだろうか。逆に、企業経営者が浮いたお金を再投資せずに貯蓄するというのであれば、将来的な見通しは暗いと考えているわけで、それなら外国人労働者など雇う必要もないわけだ。外国人労働者の賃金(相対価格)という狭い範囲しか見えていないと、お金が再投資されていくというモノとお金全体の関係(一般物価)を意識することができない。
繰り返しになるが、「デフレ期待」も「インフレ期待」も金融政策のスタンスの変化によって生じる。外国人労働者の賃金や衣料品の価格といった相対価格は、あくまでもこの大きな政策変更の影響を受けて変化するのだ。つまり、相対価格の変化をいちいち「デフレ政策」「インフレ政策」と定義してその良し悪しを判断するやり方は、原因と結果を取り違えているのである。そもそも、「価格」を決定するのは需要と供給のバランスである。これに対して、「物価」を決定するのはモノとお金のバランス(金融政策)なのだ。
日本は自由主義経済である。何を信じてどのような経済活動をするのも自由だ。誤った情報に基づいて誤った判断をしても、状況の変化で偶然それが正解になるケースもある。少ない確率に賭けて一攫千金を狙うのもひとつの生き方ではあるが、誤った判断は一攫千金どころか生活基盤の破壊をもたらす場合もあることを忘れてはならない。