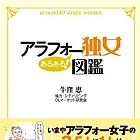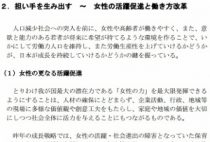「Thinkstock」より
「Thinkstock」より少子高齢化で労働力人口が減少していく中、女性の一層の社会進出を促す意味からも、時宜を得た動きといえるだろう。日本の女性管理職登用率は、主要先進国と比較して3分の1から4分の1であり、男尊女卑の風潮が強いとされる韓国とともに、最低の水準にとどまっている。
ただ、一方の当事者である男性管理職に話を聞くと、やはり否定的な声が多い。
「業種の性質上、女性には向かない部分がどうしても出てくる。数値目標を掲げるのはいいが、それではたして組織がうまく回るのか」(建設関係)
「もともと理系の女性の採用が少ないので、適任者を探すのが困難では」(精密機器関係)
「有能な女性社員は、外資系や大手コンサルタント会社に転職してしまう傾向がある」(金融関係)
異性への複雑な心理も含まれているのだろう。「長年組織に尽くして、上司が女性というのはやはり抵抗がある」という本音も聞かれた。
もっとも、法案が無事に通過しても、思惑通りに組織が女性の登用を積極化するかどうかは疑問符がつく。管理職を司り、人事についても大きな権限を持つ組織のトップ、すなわち経営陣への女性登用がきわめて少ないからだ。
『役員四季報』(東洋経済新報社)2015年版によると、女性役員自体は年々増加しているが、それでも2014年7月時点で816人だ。調査対象の役員数は3万9672人なので、全体のわずか2.1%にすぎない。これだけでも、意欲のある女性社員からため息が聞こえてきそうだが、役員の経歴を調べてみると、やりきれない現実が見えてくる。
生え抜き、すなわちプロパー社員が役員になる数は、さらに少ないからだ。先述した女性役員のうち、弁護士が112人、公認会計士は61人、医師、弁理士、社会保険労務士などを含めると180人に及ぶ。
これらは、本業が別にある兼業役員だ。また、大学教授や学校法人経営者、マスコミ関係者などが65人、キャリア官僚や各種団体出身者は28人だ。そして、創業者の配偶者や娘など同族の役員も41人いる。ちなみに、キャリア官僚については前職、同族役員については氏名や保有株式数から推計したが、実際はもっと多いのかもしれない。
働く女性の格差、さらに拡大の恐れも
上場企業の女性役員のうち、少なくとも4割近くは難関資格の所有者か前職で高い地位にいた、あるいは縁故によって経営陣に加わった落下傘役員ということになる。
一方で、内部から昇進した数は、多く見積もっても500人あまりで、全体ではわずか1.2%にすぎない。女性が組織内でコツコツと昇進して、人事に影響を与えるような地位にたどり着くのは、限りなく狭く細い道なのである。
こんな現状を考えると、自民党が唱える女性登用の数値目標は、かえって働く女性の格差を助長してしまう危険性さえある。企業が半ば強制される形で“数合わせ”に動けば、どうしても現状を踏襲する無難な選択に走りがちだ。その結果、現在以上に重用されるのは、社外で功成り名遂げた落下傘組であり、生え抜き組の余得は生じづらくなる。
(文=島野清志/評論家)
【主要国の就業者及び管理職に占める女性の割合(2012年)】
※以下、国名、就業者比率、管理職比率
(『データブック国際労働比較2014』より引用)
アメリカ 47.0%、43.7%
フランス 47.6%、39.4%
スウェーデン 47.6%、35.5%
オーストラリア 45.7%、34.7%
イギリス 46.3%、34.2%
シンガポール 44.2%、33.8%
ノルウェー 47.3%、32.2%
ドイツ 46.1%、28.6%
マレーシア 36.4%、21.5%
日本 42.3%、11.1%
韓国 41.7%、11.0%