象皮病で外出できず…医師も見過ごすがん手術後の「リンパ浮腫」、画期的治療の病院が注目
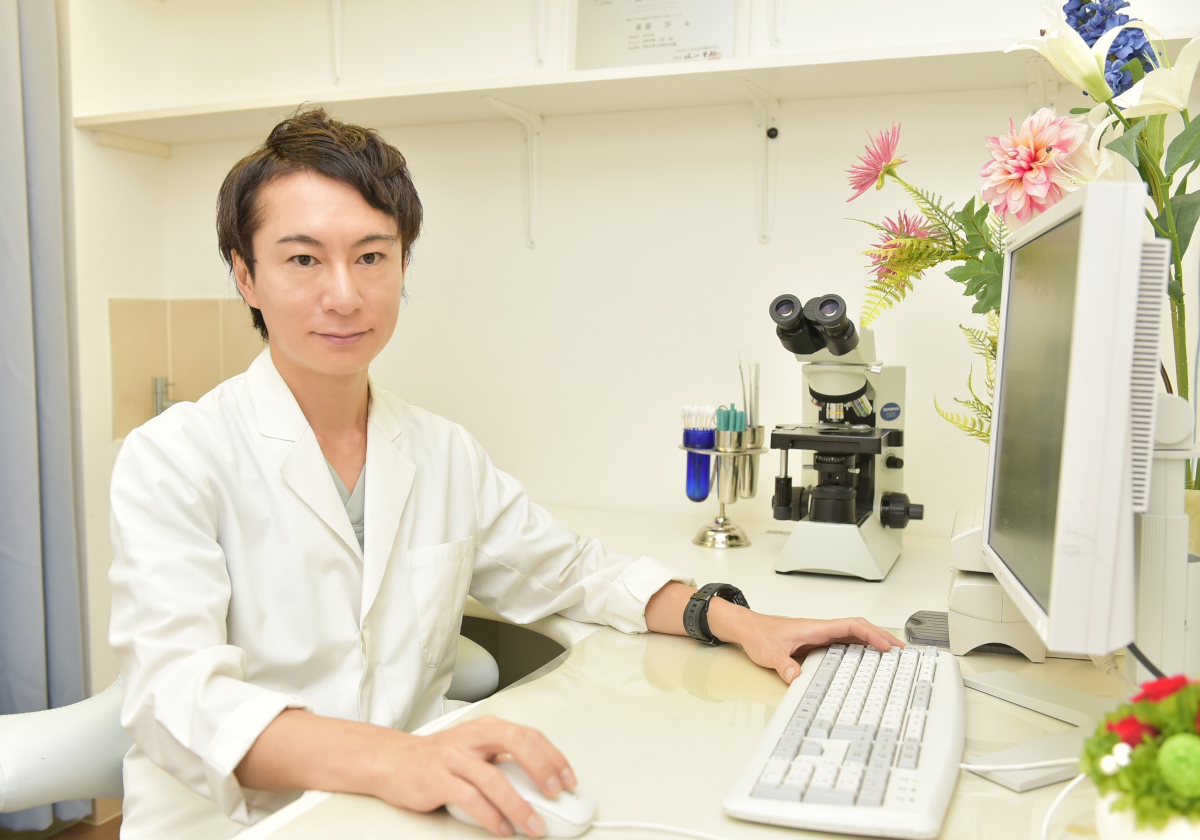
医療の進歩に伴い、がんの早期発見・早期治療が可能になり、診断後の生存率も上がっている。国立がん研究センターは12月13日、全国の「がん診療連携拠点病院」を対象に行った調査で、2010~11年にがんと診断された患者の5年生存率は66.4%だったと発表した。今や、がんは“治る病気”となりつつある。
がん生存者のなかには、病巣の摘出手術を受けた患者も多く、がん生存率が上昇する一方で術後のQOL(生活の質)の維持や向上をいかにケアするかという新たなテーマも関心を集めている。実は、術後に「リンパ浮腫」に悩む患者が多いにもかかわらず、リンパ浮腫の治療については、患者はもちろんながら医師にも広く知られていないのが現状である。
リンパ浮腫について、麹町皮ふ科・形成外科クリニックの苅部淳医師に話を聞いた。
リンパ浮腫とは
「がんの治療におけるリンパ節郭清(治療箇所付近のリンパ節の切除のこと)や、放射線治療が引き起こすリンパの流れの停滞が原因で、腕や脚のむくみのことをリンパ浮腫といいます」(苅部医師)
特に四肢に発症するため、日常生活の動作(ADL)やQOLの低下は著しい。苅部医師によると、特定のがんの手術がリンパ浮腫を起こしやすいという。
「特に乳がんや子宮がん、卵巣がんの婦人科系がん手術においては、がんの転移を考慮し、病巣付近のリンパ節を切除する『リンパ節郭清』を行うことがあります。多くのリンパ管が集まるリンパ節を切除するため、リンパ液の流れが停滞することで浮腫が生じます。リンパ浮腫は、乳がん手術でリンパ節郭清をした方のうち10~20%、婦人科系疾患によるがん手術でリンパ節郭清をした方のうち30~35%発症するという報告があります」(同)
また、発症時期には個人差があり、術後すぐのこともあれば、10~20年経過してからのこともある。婦人科の医師はがんを治すことにフォーカスし、がんを切除すればすべてが完了したかのように考えるケースも多いという。
「リンパ浮腫は20~30万人の患者がいるといわれています。残念なことですが、術後に浮腫が出るのは当たり前の現象です。だからこそ、症状が進行しないうちに治療が必要です。しかし、多くの場合、主治医にも見過ごされ、大きく腫れて日常生活が滞り、象皮病となってスカートもはけなくなってから駆け込んでくる方が少なくありません」(同)
上肢や下肢に左右差などが見られるようになったら、すでにリンパ浮腫が進行している状態だという。進行を防ぐには早期発見が重要である。
リンパ浮腫の診断

従来の代表的な検査方法は、「SPECT-CT」「MRIリンパ管造影」などであったが、造影剤の使用が患者の負担となり、検査が難しい場合もあった。患者の負担を軽減するために苅部医師がクリニックで推奨するのは、2017年に確立された超高周波超音波である。超高周波超音波は、造影剤を使用しない診断、治療が可能であり、体への負担を大きく軽減することができた。
「この検査をできる医療機関は日本でも限られており、麹町皮ふ科・形成外科クリニックでは、亀田総合病院と連携して最先端の治療を行っています」
リンパ浮腫の治療には、圧迫療法が大切だという。
「当院ではリンパ浮腫専門ナースが在籍しており、専門的な圧迫療法をきちんと指導します。また、細かな周径を測り、オーダーメイドのストッキングを作成いたします」
苅部医師は、多くのリンパ浮腫の患者を治療してきた経験から、日本の医療のあり方を変えるべきだと言う。
「リンパ浮腫に限ったことではありませんが、がん生存者に対して『助かったのだからいいじゃないか』といった考えの医師がいることが非常に残念です。確かに、がんになり、命の危機を感じた患者が助かったことは素晴らしいですが、助かった後にそれまでと同じように日常生活が送れないとしたらどうでしょうか。女性がスカートをはけない、外出も思うようにできない、という状態になった患者の気持ちを考えなければなりません。可能な限りQOLを落とさずに治療するのが、医師の使命だと私は考えます」
リンパ浮腫の治療を行うクリニックは全国でも少ない。苅部医師は、リンパ浮腫を広く知ってもらうよう各地での講演など啓蒙活動も行っている。リンパ浮腫を疑う患者や、これからがん手術を控えた患者の相談も受けている。苅部医師の活動は、これからのがん治療に一石を投じている。がん治療とQOLの維持が今後のキーワードとなることは間違いない。
(文=吉澤恵理/薬剤師、医療ジャーナリスト)





















