三浦春馬さん死去、遺族への誹謗中傷の法的問題点…死者への名誉毀損は成立する
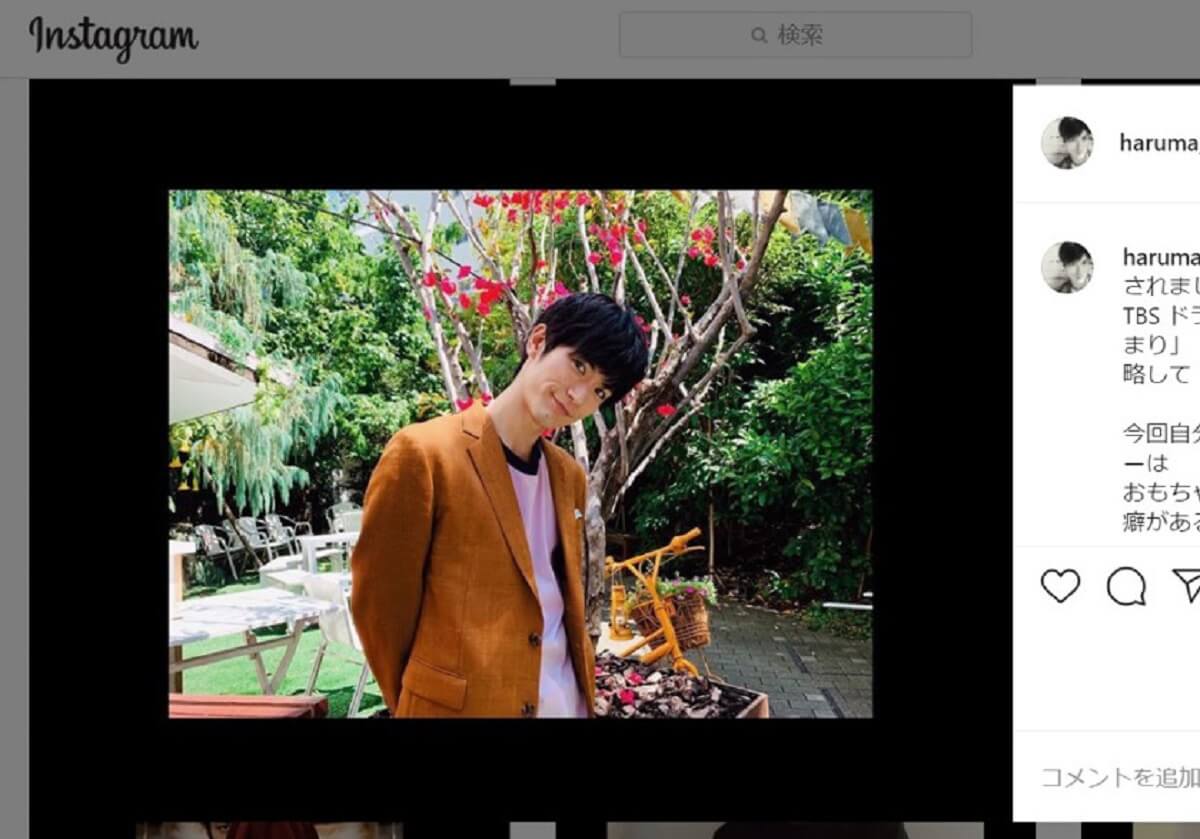
人の噂も75日といいますが、三浦春馬さんの衝撃の死から75日にあたる10月1日を過ぎても、その死を嘆き悲しむ声はあとを絶ちません。突然の悲劇の理由が明らかになっていないだけに、親族や友人、仕事関係に関する過剰な憶測や誹謗中傷もみられますが、亡くなった方はこうした憶測などに対してなんの権利も有していないのでしょうか。前回に続いて、銀座ヒラソル法律事務所の古谷野賢一弁護士に聞きました。
――一般論としてお伺いしたいのですが、お亡くなりになられた方への名誉毀損は法律では認められないのでしょうか。
古谷野 刑法230条2項に死者の名誉について「死者の名誉を毀損(きそん)した者は、虚偽の事実を摘示(てきし)することによってした場合でなければ、罰しない」とあります。生存中の人の名誉毀損は真実か虚偽の事実かにかかわらず成立し得ますが、死者の場合は、虚偽の事実を摘示した場合でないと名誉毀損罪は成立しないのです。
――死者の名誉が毀損されていることを放置したくない場合には、どうすればいいですか。
古谷野 まず、死者の名誉が毀損された場合には、加害者が虚偽の事実を摘示した場合でないと名誉毀損罪は成立しませんが、名誉毀損罪には過失犯を処罰する規定がなく、故意犯でなければ処罰されません。そのため、誤って虚偽の事実を摘示してしまった場合には、罪とはなりません。
また、名誉毀損罪は親告罪とされており、死者の名誉が毀損された場合には、死者の親族または子孫が告訴しないと罪に問われることはありません。そのため、死者に対する名誉毀損で罪に問われる場合は相当限定されてしまいますが、死者の親族または子孫が被害届を提出し、告訴することになります。
――ご親族や関係者への誹謗中傷が行なわれた場合、方法はないのでしょうか。
古谷野 死者と同時に遺族や関係者など生存者の名誉も毀損している場合には、虚偽でなくても罪に問うことができる可能性があります。また、民事上の責任追求としては、死者は死亡と同時に権利の主体(=その人本人が主体となって権利を持ったり義務を負ったりする資格)ではなくなってしまうため、死者自身が損害賠償請求を行うことはできませんが、死者の名誉が毀損された場合において、それが遺族の死者に対する敬愛追慕の情を侵害したものとして、遺族からの加害者に対する損害賠償請求を認める裁判例が多数あります。
この場合には、裁判所は、摘示された事実の重大性、遺族と死者との関係や名誉毀損行為の程度態様のみならず、行為者の虚偽の事実であることについての認識の有無も考慮し、総合的に判断することが多いようです。さらには、原状回復としての謝罪広告が認められる場合もあるようです。
加害者に損害賠償請求
――誹謗中傷の対象となるのは?
古谷野 職場や学校などでの噂話、テレビ、ブログ、Twitter、Instagram、YouTube、LINE、雑誌や新聞、書籍、オンライン上の記事など、あらゆるものが対象となります。一例を挙げると「らしい」「だそうだ」「誰々が言っているのを聞いた」など、さも事実のように書いたりしているものも該当します。亡くなった方の名誉毀損については、親族から加害者に損害賠償請求を行うこととなります。
まず、加害者と名誉毀損行為を特定したうえで、加害者に対して損害賠償請求を内容証明郵便で行います。この段階で双方が話し合って示談で解決できる場合もありますが、それができない場合には裁判所に訴訟提起を行うことになります。
――名誉毀損で罰せられるとしたら、どんな刑事罰が下されますか。
古谷野 3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処すると法律で定められています。
――三浦さんのケースに限らず、第三者が心配するあまり、悪気がなくても噂を信じ、拡散した場合でも、その行為が過剰で、その裏付けが取れた場合は、法的手段を取られる可能性はありますか。
古谷野 可能性としてはあり得ます。周囲が流している情報を安易に鵜呑みにすることはせず、ご自身が真実を知っているのか、発言や発信することによって他を傷つける可能性がないかということにも考えを及ばせて、今一度、冷静になられることが大切かと思います。
自死された方の遺族の苦しみ
筆者の知人に、三浦春馬さんがお亡くなりになられる少し前に一緒に仕事をした人がいます。それほど深い関係ではなかったようですが、爽やかで透明感に溢れた笑顔で去っていった三浦さんに、なんの異変も感じられなかったと言います。「個人的にも大好きな俳優さんだった、努力家で、礼儀正しく、優しく、謙虚で、つねに細やかな配慮のできる人だった。誰も三浦さんのことを悪く言う人はいなかった。これからさらに輝く未来が待ち受けていると信じて疑わなかった。責任感に溢れた三浦さんが、撮影中になぜ? と……」と言葉を詰まらせていました。
知人ですらそうなのですから、ご親族や友人、親しい仕事関係の方は、耐えがたい悲しみから抜け出せないでいらっしゃるかもしれません。その上、言葉のナイフで心をえぐられるような憶測や誹謗中傷に悩まされ、目の前の苦しみに耐え、次の一秒の辛さを乗り越えて、日々を過ごしていらっしゃるのではないかとお察しいたします。
特にご親族は、あまりに突然過ぎる出来事に、ご自身を支えるだけで精一杯の状態ではないでしょうか。ファンの方が心配したり、いろいろと知りたいというお気持ちを理解できても、体調を崩されたり、「そっとしておいてほしい」と思っていらっしゃるなら、周囲はそのお気持ちを尊重し、見守ることしかできない状態なのかもしれません。
三浦さんのキレキレのダンスのCMを見て以来、にわかファンになっていた私にも、三浦さんにいったい何があったのか、知りたいことは山ほどあります。でも、その一方で、ある知人の顔を思い出しました。知人は20年前に家族が自死した際の第一発見者でした。その日の朝の食卓は、週末の家族旅行の話で盛り上がり、その後、それぞれが外出した、ありきたりな一日の始まりだったそうです。ところが、知人が自宅に戻ると、変わり果てた家族の姿を発見してしまったのです。その方はこう言います。
「本当に仲の良い家族だったはずなのに、『なぜ?どうして?』と、当初2~3年は生きる屍のようになり、あとを追うことだけを考えていた。次第に亡くなった原因を探そうとしたけれど、結局、原因は不明のまま。20年が経過した今でも原因がわからないから、自分を責めることしかできず、時折、感情がフラッシュバックして、突然、声をあげて泣いてしまう。
人には家族が自死したことを明かしていない。それは人を信用するとかしないとかではない。自分の一番奥底に封じ込めた気持ちを解放する気にはなれないから。いっそ、忘れられる日が一日でもくるかもしれないと思って、前向きにいろんなことにチャレンジしていると、『あなたに会うと元気が出る』と言われる。本当は私の人生は自死を発見した時から、時間が止まっている」
こう泣きながら打ち明ける姿を前に、かける言葉など何一つありませんでした。
10月25日には三浦さんがお亡くなりになられた日から100日後の法要にあたる「卒哭忌(そっこくき)」を迎えます。「卒哭」とは、ご親族などが慟哭することを卒業することを意味します。泣き明かすのをやめて一区切りをつける仏教の考え方で、忌明けという人もいます。
三浦さんのご親族や知人、仕事関係者にとっては、たった100日で深い悲しみを卒業することなど、到底できないことだと思います。その死を受け入れることすら、一生かかるかもしれません。
自死の理由は、ひょっとしたらご本人にもうまく説明がつかないことかもしれません。いずれにせよ、はっきりしているのは、三浦さんは、もうこの世に存在しないこと、その死の理由は永遠に不明だということです。
「無念」と思うファンの気持ちは当然でしょう。しかし、心配するあまりであっても、確証のない話を拡散したり、誹謗中傷は死者の名誉を傷つけます。場合によっては刑事罰を受けることもゼロではありません。何より、三浦さんはファンが罰せられることを望んでいらっしゃるでしょうか。
12月11日から三浦春馬さんの主演映画『天外者(てんがらもん)』が公開されます。ファン歴の浅い私が言うのもおこがましいですが、天国の三浦さんに新天地で笑顔に溢れる毎日を過ごしていただくために、今はただ三浦さんが遺した作品の数々をいつまでも忘れずに愛し続けることが、何よりご冥福を祈ることになるのではないかと思うのです。
(文=鬼塚眞子/一般社団法人日本保険ジャーナリスト協会代表、一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会代表)





















