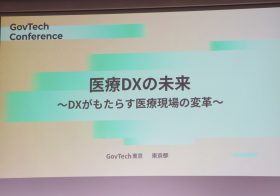若者、原因不詳の自殺増加が社会問題に…「スマホつながり」にすがる不安と孤独

コロナ禍の昨年、自殺者数は11年ぶりに増加した。自殺者数は1998年以降14年連続で年間3万人を超えていた。2006年に自殺対策基本法が制定され、ウエイトの大きかった中高年の自殺者数が大幅に減少し、昨年の総数は2万1081人にとどまっている。
しかし若者に関しては、相談窓口を増加させるなどの対策はされてきたものの、増加傾向にある。昨年の10代、20代の自殺者数は3298人となり、前年に比べて2割近く増加した。なかでも深刻なのは、自殺の原因がはっきりしない例が多いことである。
自殺の太宗を占めていた中高年の場合は、リストラや会社倒産などの経済面での困窮や病気など原因が明確だったが、10代、20代の場合、警察などの聞き取りなどでは原因がわからず、「不詳」とされるケースは3割に上っている。
このような状況にかんがみ、NHKは6月13日、『若者たちに死を選ばせない』と題する特集番組を放映した。番組では「なぜ若者たちは死を選んでしまうのだろうか」「家族など周囲にいる人たちはどんなことに気をつけたらよいのか」という視点から、その解決法を模索している。番組の中で臨床心理士が「コロナの影響でどんどん若者たちの居場所がなくなり、生きづらさを感じている」と述べているが、どういうことだろうか。
増殖を続ける“ゆるキャラ”
「ぼくが子どもの頃は、よくわからないけど、社会や人間に対する信頼があった」
このように語るのは『スマホを捨てたい子どもたち』の著者、山極壽一・前京都大学総長である。1952年生まれの山極氏の子ども時代とは異なり、現在の子どもたちにとって世間は自分を守ってくれるものではなく、絶えず情報を得て不断の努力を続けなければ冷たく自分を見捨てる存在となりつつある。つながれる人間は家族でも先生でもなく、自分と同じ境遇のわずかな仲間に限られ、スマホという情報端末にすがっているが、「情報を読み間違えたらつながりが切れてしまう」と不安を抱えて毎日を過ごしているという。
IT革命を身近に感じて育ったデジタル・ネイティブと呼べるZ世代(1990年代後半から2000年代生まれ)は、情報収集能力があり多様な価値観を認める姿勢がある一方、対面で踏み込んだ批判をされることに過敏であるとの指摘がある。「スマホつながり」が若者たちに安心感や充足感を与えていない状況下の日本で注目すべき現象は、列島のあらゆる場所で増殖を続ける“ゆるキャラ”である。
ディズニーのミッキーマウスをはじめ、動植物を擬人化したキャラクターは世界中に見られるが、その数と活動量において日本のキャラクターは群を抜いている。コロナ禍でも日本のゆるキャラたちはマスクを配るなどパンデミック収束を目指した啓発活動を懸命に行っている。大量のゆるキャラが誕生しているということは、それを求める社会的需要があるからにほかならない。
「(ゆるキャラは)現代社会の息の詰まるような人間関係のクッションであり、ストレスの重圧に折れそうになる心の癒やしだと考えている」
このように主張するのは『日本人と神』の著者、佐藤弘夫・東北大学名誉教授である。若者たちの生きづらさの背景には息の詰まるような人間関係があり、緩衝材として機能しているのである。ゆるキャラとの出会いが、心に溜まった澱(おり)を一気に昇華させるカタルシスの効果を有するというわけである。近代化の名の下に社会からカミを閉め出した現代人が、自らを取り巻く無機質な光景におののいて、その隙間を埋める新たなカミを求め、その先に生まれたのが無数のゆるキャラだったのである。
しかし、ゆるキャラはかつての日本の共同体の核となっていたカミにはなれないだろう。前述の山極氏は長年にわたるゴリラ研究を通して、「人間はこれまで、同じ時間を共有し、『同調する』ことによって信頼関係をつくってきた」と主張しているが、筆者が注目するのは「ダンスを踊る」という同調行為である。人間は二足で立つことで上半身と下半身が別々に動くようになり、身体でいろいろな表現ができるようになった。「踊る」という行為を通じて離れた状態のまま他人の身体と自分の身体を合わせることができ、これが共感の源となった。人間はこれにより新たな社会性を持つことができるようになったのである。ダンス活動が参加者の共感性に良い影響を及ぼすことを実証する研究がある。
ダンスが日常となる社会
コロナ禍も加わり、生身の人間としてつながることができにくくなったネット社会が、生物としてのヒトにとって不快なのは当然である。世界的に見ても若者の閉塞感が深刻であるとされる日本だが、希望もある。
日本では世界初のストリートダンスのプロリーグ(Dリーグ)が今年5月にスタートした。ストリートダンスは、1970年代の米国の路上で誕生したが、日本でも人気が高まり、国内の競技人口は約600万人に達し、10代以下や女性の比率が高いという。
日本では2012年から中学校体育で男女ともにダンスが必修化となり、小学校の学習指導要領にも「表現運動」としてのダンスが組み込まれている。欧米とは異なり日本でダンス文化は必ずしもメジャーではないが、若い世代は「リズムに合わせて楽しく動こう」という本来の意味でのダンスを理解しており、今後「ダンスが日常となる社会」になるのも夢ではないとの声も聞かれる。
日本ではかつて「盆踊り」が村の結束を強める機能を果たしてきたという歴史がある。即効性はないかもしれないが、若者たちが死を選ばない社会にするためには、彼らの間で芽生えつつあるダンスを地域社会に根付かせていくことが有効なのではないだろうか。
(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)