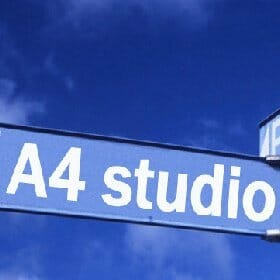7月1日、愛媛県松山市にあるラーメン店「鶏白湯専門店KANEOKARAMEN」でラーメンを食べた19人に下痢や腹痛などの症状が現れ、食中毒と診断されたニュースが話題となった。同店のラーメンを食べ、食中毒の症状が出たあるTwitterユーザーのツイートは10万“いいね”以上を記録し、続くツリーでは「衛生観念はどうなっているのか」と店への批判が殺到していた。
今回、物議を醸しているのは、ラーメンにトッピングされた半生だといわれている鶏チャーシュー。鶏肉といえば、生の状態だと「カンピロバクター」という細菌が高確率で付着しており、食中毒を起こす危険性があることで有名。同店で提供されているラーメンの写真を確認すると、問題の鶏チャーシューの中心部はピンク色であり、「生の状態にしか見えない」と指摘する声があるのも頷ける。
生に近い状態の鶏肉を食べることは、多くの人にとっては避けたいこと。しかし、九州では生の鶏肉を食べる習慣があり、飲食店やスーパーマーケットでも提供されていることが珍しくないという。現状、国には生食用の鶏肉に関する衛生基準はないものの、九州ではいくつかの県が独自で生の鶏肉の提供に関する厳格な基準を作っているようだ。SNS上では今回のKANEOKARAMENの騒動を受け、しっかりと基準を定めて生の鶏肉を提供しようとする九州の取り組みを評価する声は多かった。
そこで、今回はフードアナリストの重盛高雄氏に、KANEOKARAMENの衛生に関する意識や、九州で生鶏肉がどんな基準で提供されているのかについて伺った。
KANEOKARAMENの衛生への配慮、鹿児島独自の基準とは?
はじめにカンピロバクターがどれほど恐ろしい細菌なのかについて、改めて確認したい。
「カンピロバクターは、鶏、牛などの家畜、ペット、野生動物と、多くの動物が保菌する細菌です。主に生の状態の鶏肉を食べることで発症し、下痢、腹痛、発熱、悪寒などの症状が引き起こされます。厚生労働省によると、年間300件、患者数は2000人近くも出ており近年は増加傾向にあるようです。
カンピロバクター食中毒になる主な理由には、鶏肉を生や加熱不足の状態で食べてしまうことが挙げられます。そして、鶏肉を調理した器具の衛生面が悪い場合も発症する可能性は高まるので、鶏肉自体は加熱できていても食中毒を引き起こすケースもあるんです」(重盛氏)
今はコロナ禍の影響によりアルコール消毒液を置くお店が当たり前となり、人々の衛生に関する意識は高まったと思われる。だからこそ今回のような事件は、より注目を集めたのだろう。
「KANEOKARAMENのFC本部である株式会社OMOの公式サイトを拝見したところ、衛生管理についての記述は多くありませんでした。半生と思われる鶏チャーシューを取り扱っているお店を運営しているにもかかわらず、そうした衛生面への意識が低かったのだとしたら驚きです。飲食店では、食の安心・安全の保障が基本となるため、今回のような事件は非常に残念でした。
それにOMOは、味、美味しさをアピールするというより店舗デザインに力を入れている印象を受けました。もちろん、店舗デザインやおしゃれな器など料理が美味しいと思えるようなパーツづくりも大切ですが、飲食店ならば味と安全を第一に主張することが重要ではないでしょうか」(同)
例えば鶏の生食が盛んな鹿児島県では、県独自の基準を用いて生の鶏肉を提供しているという。
「鹿児島県では、江戸時代に武士が士気高揚を図るべく闘鶏を行うことが盛んであり、負けた鶏はその場でしめて生で食べていたそうです。その後、生食は庶民にも広まり、今日の『鶏刺し』に代表される生の鶏肉を食べる習慣につながったのだといわれています。つまり、鹿児島県民にとって鶏を生で食べることは大事な文化のひとつなんです。
鹿児島県では生食用の鶏肉の安全確保を図るべく、2000年に『生食用食鳥肉の衛生基準』を策定しました。この基準を簡単に説明しますと、カンピロバクターが陰性であることはもちろん、中抜(体から内臓を取り除くこと)の際に体へ病変、寄生虫、傷、消化管内容物を付着させることは厳禁となっています。
その後、流水で洗浄し、必要に応じて殺菌をしてから水切りを完全に行って、すみやかに10度以下に冷やします。そして、清潔で衛生的な合成樹脂製などの容器に保存し、運搬しなければなりません。また飲食店も『表示基準目標』を店内に掲げなければならず、食中毒のリスクがあることを明記して提供することになっています。このように細かい決まりを守らないと、生の鶏肉を提供できない仕組みになっているんです」(同)
なお宮崎県でも07年に「生食用食鳥肉の衛生対策」を定めるなど、独自の衛生基準をもって生の鶏肉を提供しているようだ。
決してノーリスクではない、生の鶏肉を食べるうえでの注意
とはいえ、鶏肉は原則として加熱が前提であり、仮に鹿児島県の基準を守ったとしても食中毒のリスクはゼロではないという。
「どんなにお店側が基準を守ったとしても、食べる側の免疫力が落ちていたり、食中毒に対する抵抗力の弱い高齢者や子どもが食べたりしたときは、食中毒が起こる可能性は決して低くありません。なので、明らかに火が入っていないといえる色合いの鶏肉であれば、自分の体調を考慮して食べる・食べないの判断をするのがいいでしょう。とはいえ、口に入れてから生だとわかるものもあるので難しいところではありますが……」(同)
また「自分は食中毒にかからない」といった根拠のない自信を持って生肉を食べるのは危険だと重盛氏は指摘する。
「11年に『生食用食肉の規格基準』が策定される以前は、焼肉屋、居酒屋でユッケや生レバーなどの生肉が食べられました。ほんの10年前まで気軽に生肉を食べられたので、策定以前の緩い危機感で生肉を食べている人は現在もかなりいるのではないでしょうか。
特に近年は、お店ごとの差別化を図ったり、自宅で生肉を食べるのはリスクがあったりするなどの理由で、鶏肉に限らず生肉を提供するお店が増えてきています。ですから、よりいっそうの衛生面への配慮をし、食の安心・安全が問われるような時代へ変化しているといえるでしょう」(同)
最後に今回のKANEOKARAMENの一件をきっかけに、今後の生食文化にどのような影響が出てくると考えられるだろうか。
「今回の一件を教訓に、鶏の生食は危ないからきちんと加熱すべき、という危機感が浸透していってほしいですね。その一方、きちんとした基準を守り生の鶏肉を提供するお店、業者が批判の的になってはいけないと思います。
“鶏の生食=悪”という図式ではなく、どうすれば安全に食べられるか、どんなお店が安全なのかを判断し、生食に関する正しい知識を持つことが大切です。そのような考えを持つ人が増えていくことで、鶏の生食という文化を守ることにつながっていくのではないでしょうか」(同)
正確な知識を持ってリスクと向き合う必要があるといえよう。