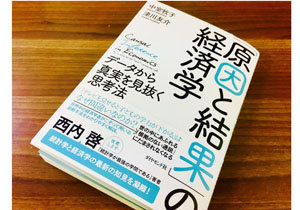 ※画像:『「原因と結果」の経済学』
※画像:『「原因と結果」の経済学』「そんなこと、考えれば当然だろう」と思っていることでも、実際データを出してみると違っていたことがしばしばある。
例えば、以下の3つの通説はそれに当てはまる。
・メタボ健診を受けていれば長生きできる
・テレビを見せると子どもの学力は上がる
・偏差値の高い大学へ行けば収入は上がる
意外だと思う人も多いだろうが、これらは思い込みに過ぎない。経済学の有力な研究によればこれらをすべて否定しているのだ。
もし、本当にこれらが正しいのならば」、「メタボ健診」と「長生き」、「テレビ」と「学力」、そして「偏差値の高い大学」と「収入」の「因果関係」が存在していなくてはいけない。
ここで大切なことは、「相関関係」ではなく「因果関係」であるということだ。
「相関関係」ではなく「因果関係」に着目しよう
『「原因と結果」の経済学』(中室牧子、津川友介著、ダイヤモンド社刊)は、非常に知的好奇心をそそられる一冊である。本書を読み込めば、これまで「当たり前」や「常識」だと思っていたことが、ことごとくひっくり返されるかもしれない。
まず、本書から「相関関係」と「因果関係」の違いを引用しよう。
――2つのことがらのうち、片方が原因となって、もう片方が結果として生じた場合、この2つのあいだには「因果関係」があるという。一方、片方につられてもう片方も変化しているように見えるものの、原因と結果の関係にない場合は「相関関係」があるという。
(『「原因と結果」の経済学』P26より引用)
「因果関係」の説明をする前に、「相関関係」の穴について書いておこう。
「因果関係」は“見せかける”ことができるので注意が必要だ。
「地球温暖化が進むと、海賊の数が減る」という主張があるとする。実際に1800年代から2000年までの2つの変数をグラフ化してみると、地球の気温は上がっているのに対し、海賊の数は少なくなっている。
しかし、その2つの変数に相関があるとは考えにくい。もし、関係があることを明らかにしたいならば、他にも変数が必要だろう。
こうした「見せかけの相関」は世の中に溢れている。いわば都市伝説のようなものだ。よく知られたところでは、日本のテレビで金曜夜にスタジオ・ジブリの映画が放送されると、アメリカの株価が下がるという「ジブリの呪い」がある。
2つの変数は因果関係にあるかどうか考えるときに、まずは出されたデータを疑ってみることが重要だ。人は分かりやすさに飛びついてしまいがちで、その心理を利用した広告やプレゼンテーションも多々見受けられる。見せかけの相関関係には注意したい。
「偏差値の高い大学へ行けば収入は上がる」のウソ
さて、「因果関係」である。
・メタボ健診を受けていれば長生きできる
・テレビを見せると子どもの学力は上がる
・偏差値の高い大学へ行けば収入は上がる
これらの通説は、経済学の有力な研究から因果関係が否定されていることは冒頭に述べた。
しかし、なんとなくだが関係はありそうである。なぜ、因果関係が否定されているのだろうか?
この中から「偏差値の高い大学へ行けば収入は上がる」について本書から説明しよう。
実際に日本の「卒業大学別平均年収」のデータを見てみても、偏差値の高い大学であればあるほど、平均年収が高くなる傾向があることがわかる。
米プリンストン大学の経済学者アラン・クルーガーらは「大学の偏差値」と「収入」の因果関係について調べようとした。
その問いは2つである。
「偏差値の高い大学に行ったから収入が高くなった」(因果関係)のか。それとも、「潜在能力が高く収入が高くなるような職業に就く人が、偏差値の高い大学を選択した」(相関関係)のか。
このどちらか、ということだ。
その調査をすすめたところ、クルーガーらはある結論に達する。
――驚くべきことに、ある大学に合格に合格して実際に進学した生徒のグループ(介入群)と、同じく合格したがその大学に行かず偏差値の低い大学に進学した生徒のグループ(対照群)のあいだで、卒業後の賃金に統計的に有意な差はなかったことがわかった。
(同・P157より引用)
つまり、偏差値の高い大学に行ったから収入が高いという因果関係は成立せず、そこには将来高収入になる人が偏差値の高い大学に行くという相関関係があったのである。
ただ、アフリカ系アメリカ人や貧困家庭については偏差値の高い大学に行ったといい、偏差値の高い大学で築かれる人脈がマイノリティや貧困層に有利に働いたのでは、とクルーガーらは解釈している。
◇
『「原因と結果」の経済学』ではすでにあげている3つの通説の他にも、「男性医師は女性医師より優れているのか」「認可保育所を増やせば母親は就業するのか」「勉強ができる友人と付き合うと学力は上がるのか」といった全6つのトピックの因果関係を探る。
世の中には根拠のない通説があふれている。信じるか信じないかはその人次第だが、真実はまた別にあるということだ。
(新刊JP編集部/金井元貴)
※本記事は、「新刊JP」より提供されたものです。





















