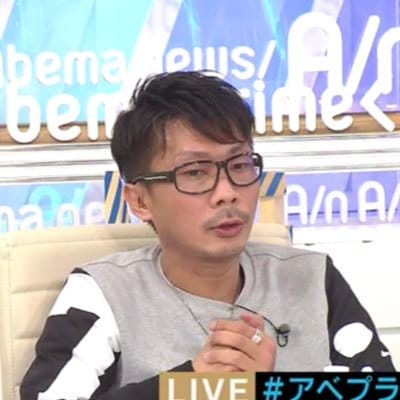神田沙也加さんの悲劇に想う、ジャーナリズムや小説が「有名人の死」を扱う意味

ドラマ『ムショぼけ』の企画をスタートさせた際、どうしても外せないテーマが「死」であった。
当初からあくまで『ムショぼけ』の原作小説は、ヒューマンドラマとして、現代社会ににおける人権や格差、そして死などといった重いテーマを選びながらも、物語としてはコミカルに描くことを目的としていた。
重いテーマを重く描くのは、はっきりいってしまえば誰にでもできる。なぜならば、読者に対して、自分が体験した苦しみに満ちた題材をそのまま、ストーリーとして伝えてしまえばいいからだ。それが悪いというのではない。ただ、私たちが選択したのは、良くも悪くも、その期待を裏切るというところにあった。
それでなければ、コロナ禍という誰しもが経験したことがない中で苦労して、わざわざ作品を作る意味がないと考えたのだ。コロナ禍にあっても、重いテーマをエンタテインメントとして昇華する力を持った作品を、しかも関西ローカルからでも放つことができるんだぞ、と世の中の人々に見せつけてみたかった。それは、物語に携わってくれた人々、すべての想いでもあったといえるだろう。
その中でも、大切なことは作り手の自己満足で終わってはならないということだ。観る側の共感を得て、人々の記憶に刻み込まれることができなければ、意味がない。では、共感を得るためには、何が必要か。それは実社会に横たわるリアルだ。
『ムショぼけ』の中で、ヒロインの人気タレントであるリサは自ら命を断つ。この設定をするのに、私は相当な悩みがあった。登場人物たちの生みの親である書き手の私は、彼らに生命を吹き込むべく心血を注ぐ。特に筆を走らせていくうちに、キャラが際立ってきた人物に対しての想いはなおのこと強くなる。ゆえに、物語上とはいえ、そんな人物を死なせることは簡単にできることではない。だが、自殺という社会に横たわるリアルを描くこと、『ムショぼけ』という物語の中でリサが自殺をすることは、ヒューマンドラマとして視聴者や読者に投げかける上で必要であった。
そこで投げかけたいことはシンプルだ。どんな理由であれ、愛する人が自殺した時、残された側はどれだけのやりきれなさを抱くかということだった。
物語を執筆するときは、当たり前だが、ひどく感情移入するもので、以前にも死刑囚をテーマにした小説を書いたときは、その道中は辛くて辛くて仕方がなかった。文章力がどうとか物語がどうとか以前に、書き手にそれくらいの想いがなければ、読者の共感など得ることはできないのだ。
同じように、『ムショぼけ』のヒロインの死を描くのには、大変な苦悩があった。それでも間違いだったかといえば、そうではない。
ちょうど物語を執筆している頃、有名人の自殺が相次いでいた。それらが、他人の自殺を誘発するという見方もある。メディアが自殺をいたずらに取り上げることの社会的悪影響を危惧する声も強まった。
それらの何が正しいかはわからないが、私の場合は、社会派のヒューマンドラマを描く上で避けては通ることができないと判断した。自殺はしてはならない。自殺はなくさなければならいない。メディアが有名人の自殺報道に蓋をする必要があるのであれば、せめて小説の世界では自殺という不可逆的行為が持つ意味をしっかりと描かないといけないと思ったのだ。
他人の不幸な死から伝えることができるもの
そして、ドラマ『ムショぼけ』でヒロインが自殺を遂げる回が放送される前日、実社会においても、我が友が自ら命を断つという経験をした。物語の中で、ヒロインは最期に主人公と連絡を取る。実社会でも、友は最期に私に連絡をしてきた。両者がリンクしたのだ。ただ異なったのは、物語では、ヒロインからの最期の連絡を受けたあと、主人公はさまざまな葛藤を抱きながらも、彼女を信じ、その後も連絡をずっと待ち続けた。一方、実社会の私は、友からの普段とは異なる様子の電話が切れた後、万が一の時に後悔だけはしたくないという想いが強く、友の携帯電話の充電が切れるまで、呼び出し音を鳴らし続けた。
結局、だからといって気持ち的に救われることはない。それが人の死に接するということ。救えたかもしれないという思いの中で、大事な人を失うということなのだ。そうして、人は命の儚さや尊さを学んでいくのである。それらは、たとえ何度経験しても慣れることはないし、学び終えることはないことだ。
12月18日深夜、知り合いの記者から、神田沙也加さんが北海道でホテルの高層階から転落したという連絡を受けた際、私は大阪で起きたクリニック放火事件の取材にあたっている最中であった。いずれも、まだニュースなどで報じられる前の話だ。
自分は小説だけでなく、ジャーナリズムの現場にも携わる物書きだ。広く、深く情報を扱う会社も経営している。そんな立場で、このような重大ニュースを、テレビで報じられてから知るようなことはあってはならない。第一報をテレビで知らされたとしても、それ以上の詳細な情報や報道されないニュースの裏を知る必要があるのだ。すごいとか偉いとかの問題ではなく、情報に携わる人間の最低限の務めである。そして、それに対する分析ができなければ何の意味もないのだ。錯綜する情報に、ミーハー気分で面白おかしく接し、いちいち驚いていては事の本質などには到底辿り着くことはない。
神田さんは自ら死を選んだという見方が強いが、真相はわからない。だが、数年前にマスコミの間では、今回の件にもつながるかもしれない、あるトラブルについて囁かれたことがあった。また、神田さんの精神状態を危惧する声もあった。仮の話でしかないが、彼女に関するそうした認識を周囲が持っていれば、今日の彼女をめぐる環境も変わっていたかもしれないという思いが募る。
マスコミは、なんでもかんでも報じるわけではない。そして、報じることが、報じられた本人や社会にとってプラスなのかマイナスなのかは、その時点では評価できない。また、社会的評価云々とは別に、仕事だからこそ、マスコミは報じたがるというのも事実である。それがジャーナリズムだと大それたことをいう気など、私はさらさらない。そこにもちろん理解などいらないし、世間から必要とされなければ、マスコミは存在していないし、そのうち消えていくだろう。単純にそれだけの話だ。
だが、辛い現実にぶつかることや批判されることを避けて、マスコミや物書きが、必要であると思ったことを報じたり、語ったりすることを止めてはいけない。他人の不幸な死であろうとも、そこから命の儚さや尊さを伝えることはできるはずだ。
生きていくということは、辛いことでもある。ただ生きていくということは、1人ではないのだ。その人がいなくなれば悲しむ人間は存在するし、迷惑がかかる人もいる。死んだ人の気持ちはわからないし、それほど思い詰めていたこともあるのかもしれない。中でも有名人の死は、人々を途方に暮れさせるが、それでも私は自ら死を選択するべきではないと強く感じる。人の死を見て、それに悲しむ人々を見て、そう思うのだ。
そして、今はただ安らかにと――。
(文=沖田臥竜/作家)