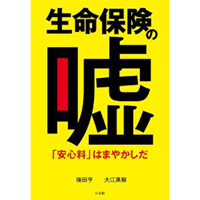「Thinkstock」より
「Thinkstock」よりその中で最近よく質問を受けるのが「ジュニアNISA」だ。教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与に続き、相続財産を軽減するチャンスと考えている人は多いようだ。しかし、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与とジュニアNISAは決定的な違いがある。そこに気づかず相続財産ばかりに目を向けていると「こんなはずじゃなかった」となりかねない。
ジュニアNISAもNISAと同様のリスクあり
鳴り物入りで始まったNISAも、2年目を迎えた。アベノミクス効果で市場の潮目が変わり、日経平均株価も2万円を超えた。NISAで初めての投資を経験した投資ビギナーも、投資のおいしさを知ったことだろう。その意味で、今はまさにNISAのメリットが前面に出ている時だ。そこにジュニアNISAの創設が決定した。
そもそもジュニアNISA創設の目的は、若年層への投資のすそ野の拡大、高齢者の金融資産を(ジュニアNISAの拠出金として)流通させる、長期投資の促進、の3点にある。
これからの世代は、今以上に資産形成が難しくなる。早い時期から時間をかけて増やしていくことは、リスク軽減の観点からいっても正しい。しかし、資金を拠出する祖父母のもくろみはどうだろう。
最近、高齢者からジュニアNISAについて聞かれることも多くなった。大半は「相続税対策になりますよね?」というもの。これについては、まさに創設目的のひとつにもあるように、自身の資産を減らすことにつながるわけだから、もちろん効果はある。
しかし、ジュニアNISAを安易に相続税対策の手段と位置づけるのは疑問だ。
もともと年間110万円までの贈与は非課税という暦年贈与の制度がある。ところがジュニアNISAで非課税になるのは年間の投資元本が80万円まで。ちなみに教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与と違い、110万円と別枠ではないので、110万円のうち80万円を使って行うことになる。それならば、あえてジュニアNISAでなければいけない理由はない。
さらに重要なのは、ジュニアNISAの場合、未成年者に代わって実際に運用するのは親権者(おそらく親)である。つまり親がきちんと運用することが大前提だ。ところが現在、成人のNISAも、口座開設数の割には実際に運用している人は少ないという。
また現状のルールでは、あくまで非課税期間は5年間なので、5年後には結果を出す必要がある。その上ジュニアNISAは期間が長いため、特に払い出し制限については成人のNISAにはないルールもある。
もちろん投資なので、損失が出てしまってもそれ自体を悪いとはいわない。ただ少なくとも親がNISAとジュニアNISAの仕組みを理解し、実際に自分の口座で運用を経験しているくらいでないと、利益に対して非課税のメリットはおろか、下手をするとせっかく贈与した資金を大幅に減らしてしまいかねない。
このように、相続財産を減らすためにジュニアNISAを活用することは、大きなリスクが伴う。相続財産の軽減であれば、むしろ従来の暦年贈与をはじめ、他の贈与特例などを利用することをお勧めする。
資金だけでなく、マネーリテラシーも育てて
現在の子どもたち、そして将来誕生する世代が、若いうちから投資に親しみ、早い時期から資産作りをしていけるよう、スタートの時点で、ある程度の資金を用意しておくことは大きな意義がある。
ただし、お金だけ与えてマネーリテラシーが伴わないのはコワイ。お金に働いてもらう以前に、まずは自分が働いてお金を稼ぐことの大変さ、重要性を子どもたちには知ってもらうべきだ。その上で年齢相応にお金との付き合い方、投資とはどういうものか、どのように向き合うのかなどを、本人たちが運用できる年齢になるまでにじっくりと会話し、伝えていってほしい。
親子三世代で資産移転を考え、子どもや孫のマネーリテラシーを育てるために活用するのであれば、相続財産を軽減させることはもちろん、リスクがあってもあえてジュニアNISAを活用する意味があるだろう。
(文=鈴木暁子/ファイナンシャルプランナー・高齢期のお金を考える会)