
近年、最新の研究によって、がん治療の効果の良し悪しに「腸内細菌」が関わっていることがわかってきた。特に、外科⼿術、放射線治療、抗がん剤治療に続く“第4のがん治療”と称される「がん免疫療法」では、腸内細菌との関わりを探る研究が進んでいる。
そのひとつに、昭和⼤学(東京)を中⼼とした「Uバンク(便バンク)」プロジェクトがある。同⼤学を中心に全国約20施設から患者の便を集めて腸内細菌を分析し、⼈⼯知能(AI)を使い、最新のがん治療薬と腸内細菌との関わりを明らかにしようというものだ。
このプロジェクトを主導する昭和⼤医学部の⾓⽥卓也教授は、こう説明する。
「がん治療と腸内細菌の関係が最初に注⽬されたのは、2015年に⽶シカゴ⼤学とフランスの研究チームが公表した『腸内細菌の違いで、がん免疫治療薬の効果が左右される』という、マウスを使った実験結果です。
きっかけは、マウスの飼育先によって、がん免疫治療薬の効果に違いがあると気づいたことです。研究チームがその原因を探ったところ、エサなどの飼育環境の違いが腸内細菌の違いにあらわれ、治療薬の効き目に影響していたことが判明したんです」
この報告がきっかけとなり、実際に薬を使っている患者の腸内細菌を調べる研究が各地でスタート。治療効果のあった患者の腸内細菌は、効果のなかった患者に⽐べ、多様性に富んでいることや、治療の前後で抗⽣物質を使っていると薬の効きが悪いことなどが明らかになった。
角田教授らUバンクが研究の中⼼としているは、免疫チェックポイント阻害剤の「オプジーボ(⼀般名:ニボルマブ)」などのがん免疫治療薬と、腸内細菌の関わりをデータから解き明かすことだ。
免疫チェックポイント阻害剤は、免疫の持つ“ブレーキ”の機能を働かせないことで、免疫細胞ががん細胞を攻撃できるようにするもの。がん免疫療法は、がんそのものに効くわけではなく、患者の免疫システムを変えるので、さまざまながんに対して効果が期待できるのも特徴だ。オプジーボの場合、悪性⽪膚がんや肺がんのほか、⾷道がんや胃がん、腎がんなどに⽤途が広がっている。
「がん免疫治療薬は、薬の効果があらわれて3年間⽣きられると、その後も5年、10年と進行せずにいられる人が多い。抗がん剤や分⼦標的薬など、従来の薬物療法に比べて優れている点です。
これをグラフ化したデータの生存曲線が“カンガルーの尻尾” に似ていることから、『カンガルーテール現象』と呼んでいます。これは、がん免疫療法だけに示さる現象です」
がん免疫治療薬の効果に腸内細菌の種類が影響
角田教授によれば、Uバンクに集まったデータの解析を進めた結果、オプジーボの効果があった患者には、ビフィズス菌などの良質な腸内細菌が多いこと、細菌の多様性があることなどがわかってきたという。
ヒトの腸内には約100兆個、約1000種類の腸内細菌が⽣息している。治療薬が効く⼈と効かない⼈には、この腸内環境の違いがあるのだ。
「良質な腸内細菌を増やして、腸内細菌の種類を増やすには、⾷物繊維を多く摂ることが効果的です。⽶国では、毎⽇50gの⾷物繊維を摂ることで、がん免疫療法の治療効果が上がるのかを調べる、前向きの臨床試験も進んでいます。
また、がんに限らず、腸内環境を変えることで病状が好転するケースとして、『炎症性腸疾患(IBD)』に対する便移植療法が挙げられます。慢性的に原因不明の難治性の腸炎が続くIBDの患者さんは、腸内細菌の種類や数などのバランスが乱れていることがわかっています。便移植療法は、バランスの整った健康な人の便を移植することで、患者さんの腸内細菌の乱れを抑制できる可能性があるのです」
腸内細菌と病気の関わりは、がんに限らず、さまざまな病とも関係があるという。たとえば、糖尿病など⽣活習慣病や、うつ病などの心の病、花粉症などに代表されるアレルギー疾患など。Uバンクでは、これまでに集まった腸内細菌にまつわるビッグデータをもとに、がん以外の病気との関わりも研究を始めている。
では、腸内環境の改善には、何が有効なのだろうか?
「ヒトが持つ腸内細菌は住む地域によっても違うので、“優れた腸内環境”は人それぞれですが、腸内細菌の種類は多いほうがいい。そのためには、腸内細菌にとって重要な“エサ”となる食物繊維を多く摂ることをお勧めします」
「⽇本⼈の⾷事摂取基準2020」で推奨されている⾷物繊維は、男性で1⽇当たり21g、⼥性で18g以上。ところが、実際の摂取量の平均値は約15g(成⼈)にとどまっているという。
優れた腸内環境から生み出される短鎖脂肪酸
「さらに注目されているのは、『短鎖脂肪酸』の存在です。短鎖脂肪酸とは、腸内細菌が食物繊維などを材料として発酵させてつくり出した有機酸(酪酸、プロピオン酸、酢酸など)。特に酪酸は、腸上皮細胞のもっとも重要なエネルギー源であり、抗炎症作用など優れた生理効果を発揮します。
ビフィズス菌などの良質な腸内細菌が増えれば、オリゴ糖や食物繊維を発酵させて短鎖脂肪酸が増加し、私たちの健康にとって良い働きをしてくれる優れた腸内環境へと導きます。
すると、『ビフィズス菌の入った食品や発酵食品をたくさん食べればいいのでは?』と考えがちですが、胃酸や胆汁酸など消化酵素によって、すべてが腸まで届くわけではありません。そこで、もともと体内にいる腸内細菌を活発化させる食物繊維が良いと考えられるので、積極的な摂取をお勧めしているのです」
がん免疫療法が効く⼈と効かない⼈の腸内細菌がどう違うのか、どの腸内細菌ががん免疫療法の効果を⾼めるのかを探り、そのエビデンスの確⽴を試みるプロジェクトは、新たながん治療の可能性を切り拓くカギとなりそうだ。
命を救う新たな選択肢を!肺がんに対する免疫療法の治験を利用した研究
( https://readyfor.jp/projects/kangarootail )
肺がん患者を救うために何ができるか(対談動画)
( https://www.youtube.com/watch?v=66RBf3S4Pgk )
(文=編集部)
※本稿はPR記事です。
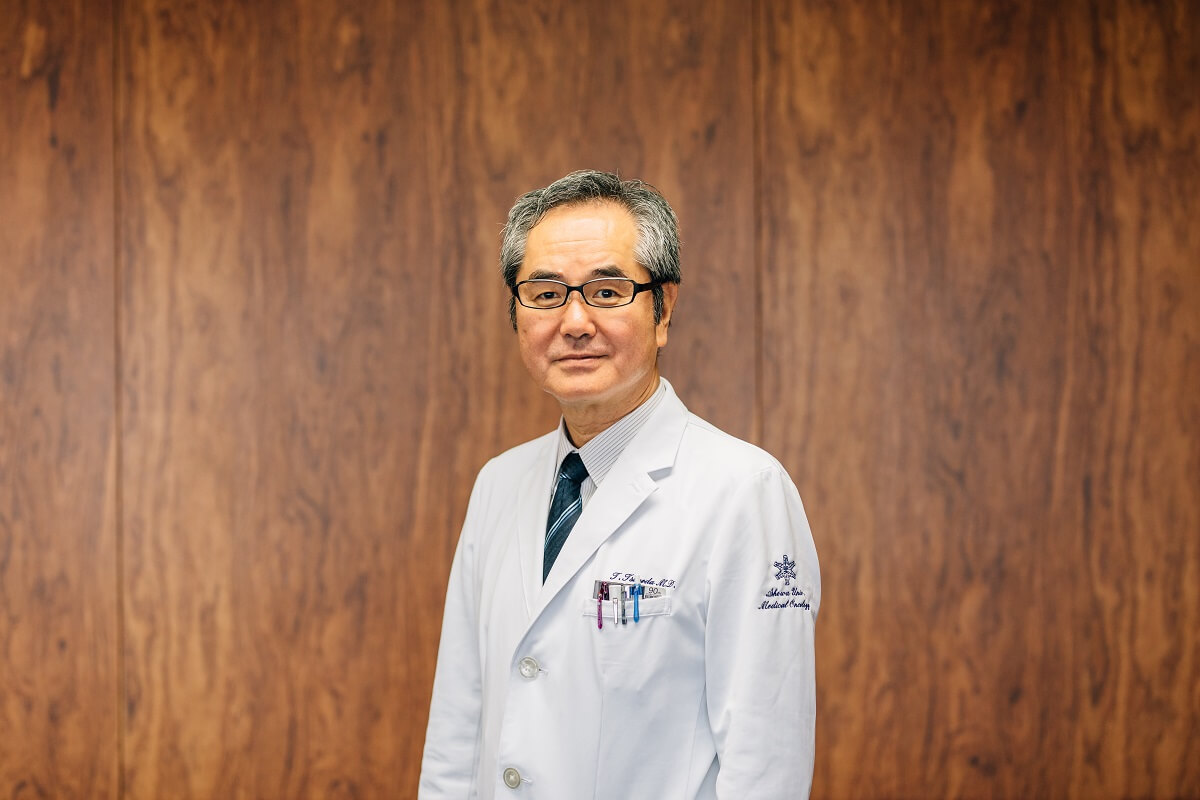
角田卓也(つのだ たくや)
和歌⼭県⽴医科⼤学卒業。⽶シティー・オブ・ホープがん研究所に留学。東京⼤学医科学研究所准教授などを経て2010年、がんワクチン開発のバイオベンチャー社⻑に就任。16年、昭和⼤学臨床免疫腫瘍学講座の教授。現在は内科学講座の腫瘍内科部⾨の主任教授。腫瘍センター長。




















